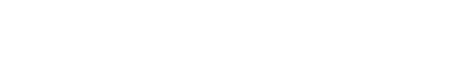おかねのね
ものの値段っていつも同じ?
ものの値段の決まる理由は色々とありますが、まず「売っているものの数と欲しい人数との関係」は重要です。例えば洋服の場合、季節の始まりには「早く買って長く着たい」と思う人がたくさんいるので定価で販売されます。しかし季節が終わりに近づくと、もう着られる期間が短いからと買うのを控える人も出てきます。そのため、売れ残り品をつくらないように、店はバーゲンセールを行って値段を下げてでもできるだけすべて売ろうとするわけです。
このように、ものの値段は、ものを売ろうとする供給側と買おうとする需要側とのバランスにおいて決まります。いくら需要が多くても供給が追いつく場合にはある程度の値上がりですみますが、果物、魚などの初モノでは、供給が少ないので、驚くほどの高値となることがあります。また1980年代後半には、転売目的での土地の買い占めが過熱したため、地価が高騰する「バブル」と呼ばれた状況も出現しました(その後、地価はバブルが破裂して下落しました)。
ここで注意して欲しいことは、高い買い物が悪く、安く買えた買い物が良いとは限らないことです。高くても長い期間大切に使い続けることができれば、使用期間に照らすと高くはないといえることもあるでしょうし、逆に安く買ったとしてもすぐに使わなくなって捨ててしまうのであれば、ムダづかいになってしまいます。値段を考える際には買った後の満足度も考慮しましょう。
用語集もご覧下さい。
もっと調べたいときには・・・
- にちぎん☆キッズ(日本銀行へリンク)
- 「お金のかち」でねだんの決まるしくみがわかります。