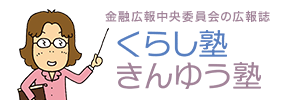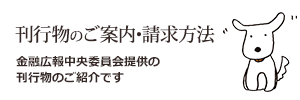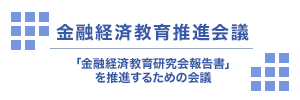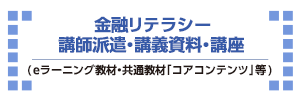著名人・有識者が語る ~インタビュー~
ミュージカルがやりたい!と、心の中で本気で望んだら、不思議と道が開けていった。大切なのは“想い”の強さかもしれません。
歌手、タレント、女優 森 公美子
圧倒的な歌唱力とチャーミングなキャラクターで日本のミュージカル界には欠かせない存在の森公美子さん。
テレビで明るい笑いをふりまき、オペラ歌手でもあり、ジャズも歌う。肩書を絞るのが難しい、生粋のエンターテイナーです。
歌に導かれたこれまでの道と、暮らしのこと、そして今の願いなどさまざまなエピソードを表情豊かに語ってくださいました。

森 公美子
(もり・くみこ)
1959年宮城県生まれ。1982年『修道女アンジェリカ』でオペラデビューし、翌年『ナイン』でミュージカルデビュー。2014年初演の『天使にラブ・ソングを~シスター・アクト~』の主演では、翌年の第40回菊田一夫演劇賞を受賞。数多くの舞台作品への参加のほか、歌手活動、テレビ出演など多方面で活躍中。
先生を驚かせた“すごい声” 勧められて始めた声楽が人生の扉を開く鍵に
幼いころから歌が大好き。
当時人気だった芸能雑誌『月刊平凡』の付録の歌本が毎号楽しみで、それを見てコードを覚え、小学生のときにはもう、ピアノでヒット曲の弾き語りを披露していたという森公美子さん。
その歌声の非凡さに気づいたのは先生たちでした。
「私、いい大人と出会ったんだと思いますね。
ちょっと歌ったとき『すごい声してるね』って言われたんです。
すごい声っていうのがどういう声か、自分にはわからなかったんですけど(笑)。
そのあと中学1年で出会った音楽の先生が、私の歌声を聴くなり『あなた、声楽やりなさい!』って。
それまで声楽が何かも知らなかったのに、面白そう!って思っちゃった」。
仙台市内の老舗旅館の“お嬢さん”として生まれ、ピアノや油絵をはじめ、1週間の予定がびっしり埋まるほど、さまざまな習い事をしてきた森さん。
なかでも声楽は特別なものに。
「すごく柔軟な両親で、子どもの中にいろんな可能性を見つけようとしてくれたんですね。
それは習い事に限らず、いろんなものに触れて育ったのは大きかった。
父はアメリカのポップスが好きだったので、私もちっちゃなころからダイアナ・ロスとかシュープリームスとかを聴いていて、自然とそういう歌が体の一部になっていたんですよ。
だから、本当はクラシックの声楽向きじゃなかったのかもしれないんだけど(笑)。
でもね、このクラシックがまさに“身を助く”で。
大学に入る前にどうしてもニューヨークに行きたくて、自分の歌を吹き込んだテープをジュリアード音楽院に送って、声楽科のサマースクールの入学審査を受けたら見事パス。
それが、音楽への道を歩き始める最初の一歩になりました」。
イタリアで大きな挫折を経験 ミュージカルとの出合いで復活

帰国後、昭和音楽短期大学に入学し、卒業と同時に二期会オペラスタジオの研修生になった森さんは、勉強のためイタリアへ。
しかしそこで味わったのは、途方もない挫折感でした。
勉強漬けの日々に疲労困憊するなかで、気づいてしまった圧倒的な経験の差。
お母さんのおなかの中にいたときからオペラを聴いていたようなイタリア人との間の、とうてい埋められるとは思えない隔たりに、打ちのめされたといいます。
「目の前にあるのは分厚い壁どころの騒ぎじゃない。
壁の上に塔まで立っているような感じ。
それを飛び越えるのはまず無理で。
地道に掘り進んでいくしかないんだろうなと思ったとき、もうどうしたらいいかわからなくなってしまった。
すでに努力も限界に思えて落ち込みました。
でもこの挫折があったから、今の自分があるんだと思う。
ここからなんですよね、私の逆転人生は!」。
どん底の気分のまま、ロンドンに住んでいた親戚の家を訪ねたときのこと。
叔母さまが気晴らしにと誘ってくれたミュージカル『マイ・フェア・レディ』を観て、演者たちの楽しげな表情に、森さんは度肝を抜かれます。
それは、張り詰めた空気の中、緊張感の漂うオペラの舞台とはまったく違うものでした。
「こんなに笑顔で演じられるって、なんて私に向いてるんだろうと思った。
それと同時に、イタリアに来てから忘れていた笑顔を思い出したんです。
父に『おまえは笑顔がいいんだからな。ちゃんと笑顔で暮らしてるのか?』って言われたこととも重なって、ああ、そうか、笑顔で勝負だ!って。
自分を見つけた気分でした。
それまでの私は気持ちに余裕が全然なくて、料理が得意なのにイタリア料理も作らず、イタリアに染まろうともしていなかったのね。
ロンドンから帰ってからは、スローな“イタリア時間”にイライラするのはやめて、笑顔で心を開いたら、やっと自分の中にイタリアが入ってきたんですよ。
それまでの苦しい3カ月は何だったの?っていうくらい、イタリアが大好きになりました。
イタリア語も、毎日バルでおじちゃんたちに教えてもらって、すっごく上達したんです」。
ミュージカルをやるんだ!と心の中で決めて帰国。
すぐにオペラデビューを果たしますが、そのあと、何かに導かれるように、ミュージカル出演への道が開かれていきます。
「オペラスタジオの踊りの授業で私を見つけた人がいて、ここに行ってと言われるがままに訪ねた先が東宝でね。
ちょっと歌って踊ってみせたら、台本を渡されました。
実は『ナイン』というミュージカルのオーディションだったんですよ。
ミュージカルがやりたいなと思いながらもどうすればいいのかわからずにいたら、向こうからやってきた。
やっぱり“想い”って一番大切なのかもしれません。
叶うんですよ。本当に真剣に望んだなら、人の想いは何よりも速く、めざすところに届くものだと思っています」。

劇場が1つになる瞬間がある それがミュージカル最大の魅力
2014年、ミュージカル『天使にラブ・ソングを~シスター・アクト~』の初演で、帝国劇場初主演をつかんだ森さん。
以来上演を重ねるたびに多くの観客を魅了してきたこの作品の幕が、2023年11月、東急シアターオーブにて再び上がります。
「初演から数えて5回目の上演。ありがたいことです。
でも、再演を繰り返すってつらいことでもあって、正解が見つからないんですよ。
毎回、見つからずに終わってる。
今回は私に与えられた最後の機会だと思って取り組んでいて、本当にパーフェクトなものを自分の中につくろうと頑張っています。
体力面も上げていかないと!」。
このコロナ禍を経験し、舞台人として、あらためて強く思ったことがあるそうです。
「舞台って、お客さまがつくるんですよ。
お客さまがいて、ミュージカルならオーケストラがいて、演者がいて、それらが1つになる瞬間がある。
リモートじゃだめなんです。
お客さまが目の前にいるのといないのとでは全然違う。
やっぱり舞台の空気を、声を、直に届けたいし、心に残る何かを持ち帰ってほしい。
そうじゃなきゃいけないだろうと、すごく思っているんです」。
まだミュージカルを観たことがない、興味はあってもチケットを買って足を運ぶまでにはいたらない、そんな人たちを劇場に誘うなら?と聞いてみると、
「とにかく本気で歌ってますから!
どうやったら面白いものを見せられるか、出演者はみんなそれだけを考えて、1カ月2カ月と真剣に練習して舞台に立つわけですよ。
ミュージカルの魅力といったら、やっぱり一体感。
ミュージカルは台詞(せりふ)だけでストーリーも理解できるし、予習も要りません。
それこそ“推し”の誰かを目当てに行くのもいいし、そこで推しをつくるのもいい。
何か楽しんでいただければいいなって。
私ね、舞台の上で本当に楽しんでるんですよ。
歌っていて、お客様も口角が上がってくるのが見えると、うれしくなっちゃうんです」。
楽しいからごはんを作る 誰かのためにも自分のためにも
レシピ本も手がけるなど、芸能界きっての料理上手として知られる森さん。
舞台を離れたその暮らしぶりも気になるところ。
例えば仕事と家事は、どのように両立させているのでしょう。
「仕事と家事っていうんじゃなくて、どちらも“私のしたいこと”なんです。
そりゃあ、したくない家事もありますよ。
掃除とか片づけはだめで、そこはバイトにお願いしたりとか。
でもキッチンのことに関しては、自分でやりたいんです。
例えば夜中の2時に帰ってきても、豚肉が明日までもちそうになかったら『ワンタン作ろ!』ってなるくらいに(笑)」。
共演者に食べてもらおうとお弁当を作ったり、リハーサルの日は全員におにぎりと卵焼きなど簡単に食べられるものを用意したりと、とにかくマメ!
「時間がとれないっていう人は、時間の配分を工夫したらいいと思う。
『これを仕込んでおけば、あとはラク』とか。
私は時間配分を考えるのが好きですね。
でもルーズな時間も必要だし、そもそも楽しくなきゃ作らないのよ、ごはんも。
私は料理が楽しいから、コロナ禍でステイホームしてたときには豚骨ラーメンも作りました。
ネットでゲンコツを買い込んで、叩いて。
近所から『異臭がします』って言われましたけどね(笑)。
いつも友達がおいしいって言ってくれる顔を見たくて作ってたけど、なかなか家に呼べない今は、自分のためで十分。
『おいしい!んまぁ~い。』ってね。
今ならいつでも冷やし中華ができるように、自慢のタレを作ってあります」。
きっぷがよくて豪快、そんなイメージの森さんに、お金の使い方についても聞いてみました。
「預金がこれくらいだというのはきちんと把握しているので、これが入ってくるなら、ここまでは出していいか、とかはしっかり意識しています。
使える範囲がわかっているぶん、出す場面では大盤振る舞いです(笑)。
皆さんに還元はしてますね。還元しないと入ってこないんですよ、お金って」。

抱え込まずに助けを求める それはとても大切なこと
森さんには、結婚して5年目に事故に遭い、半身不随になったご主人がいます。
介護を続けてもう17年に。
「私は外で大勢の人に会う仕事だし、今はまだコロナが怖くて、施設に入ってもらったままなんです。
この間に彼は、肝臓にがんが見つかって手術もしました。
本当にね、いろんなことがありますよ。
ありますけど、いちいち凹んでいたら何もできないんで。
『早期発見でよかったねー。スパッと切れたよ!』って。
幸いその後は転移もなく順調です」。
事故が起こってすぐのころは、手だてもわからず暗闇の中。
交通事故で、健康保険が使えるケースではなかったため高額の医療費が日々かさみ、蓄えも底をつきそうになったといいます。
「ぼろぼろ泣きながら、区役所に相談に行きました。
本当に何もわからなかったから、弁護士をつけるところから1つひとつ教えてもらって。
まずは障害者手帳を取って、給付があるのでその点数の中で介護の人を雇いましょうとか、そういうのを全部やってもらった。
家もバリアフリーに替えなきゃいけなかったし、車椅子も外用と家の中用は別に必要だし。
そういうこともね、福祉課の人に相談しながら、1つずつクリアしていったんです」。
すべて自分が担うべきものと思っていた介護も、人に頼っていいのだと気づいたことで救われたのだそう。
「あのね、プロがいるんですよ。プロに任せればいいんです!
日本はこれから、もっともっと福祉大国になっていかなきゃいけないと思うんですよね。
どこよりも高齢者が多くなる国だと、もうわかってるんだから」。
森さんが強く訴えるのは「助けてください」という言葉の大切さ。
「ほとんどの方が『助けてください』は恥ずかしい言葉だと思っていて、いざというとき言えないんです。
私はね、主人の車椅子を押していて、段差で『あ、これは上がらないな』と思ったら、大きな声で『手伝ってください!』って言いますよ。
そしたらひょいと上げてくださる方がいる。
本当は皆さん、手伝う準備はしてらっしゃるんです。
だから『助けてください』は、それを言う側だけじゃなくて、手を貸す側にとっても必要な言葉。
素直に言える、やってあげられる、そういう世の中になればいいなあ。
みんなが優しい、そういう国にしていかないといけないんじゃないかなあって思うんですよ」。
歌の力と自分の可能性を信じて挑戦を続けていきたい
歌の持つ力を森さんが実感したのは東日本大震災のとき。
公演中だった『レ・ミゼラブル』の千秋楽を終え、出演者たちを連れて被災地を訪ねたのは、6月になってからでした。
「石巻の中学校で『ユー・レイズ・ミー・アップ』っていう歌を歌ったとき、教室全体が嗚咽に包まれたの。
たぶん子どもたちは、泣いちゃだめだって、ずっと我慢してたと思うんですよ。
そのガチガチに自分を縛っていた何かを、歌でちょっと緩めることができたのかもしれない。
支えてあげられたのかもしれない。
歌うことしかできない、がれきの1つも片づけられない私たちだったけど、これでよかったんだと思えた瞬間でした。
音楽の力を信じられたし、むしろ私たちが元気をもらえた。
あの日のことは、きっと一生忘れないと思います」。
涙ぐみながら話してくれた森さん。
音楽の力で人を幸せにするために、今、新たな取り組みも。
「ボランティアで、障がいのある人たちに歌を教え始めたんですよ。
私は歌が専門だからそれしかできないんですけど、歌での楽しみ方を伝えたり、そういうコミュニケーションを通じて、皆さんに笑顔になっていただけたらと。
障がいって、100人いたら100通りじゃなく、それこそ3,000通りくらいあるから、ちゃんと向き合っていくとなると、自分だけではとてもできない。
いろんな人を引っ張ってきて、介護する人たちも巻き込んで、音楽を分かち合う楽しい瞬間をつくれたらいいな。
難しいこともあるだろうけど、障がいのある人たちを、まずはちょっとでも楽しませられたらと思っています。
この活動は、ライフワークとしてずっとやっていくつもり。
賛同して手伝ってくれる、一緒に歌ってくれる、ミュージカルの仲間を探しているところです」。
53歳で『天使にラブ・ソングを~シスター・アクト~』のデロリス役と出合い、その役を10年間ブラッシュアップし続けてきた森さん。
さまざまな役への挑戦はもちろん、2022年から本格的にジャズ歌手としての活動も始めるなど、歳を重ねるごとに可能性の幅を広げています。
「これから先のこと?どうなるかわからないけど、やりたいことをやる!
それは『やりたくないことはやらない』っていうのとはちょっと違うんですよ。
その『やりたくないこと』のなかに、もしかしたら、とても私に向いていることがあるかもしれない。
だから常にいろんなことに挑戦していたい。
やってみたら面白いことって、たくさんあると思うので。
舞台もね、私は『主役じゃないと嫌、端役はやりません』なんて言いませんよ。
だってそんなのつまらない。
来た役はみんな試してみて、私なりに面白く演じてみせるっていうスタンスです。
いくつものポケットから毎日違う自分を取り出して、演出家に『どれにする?』って見せていきたい。
自分の可能性は1つじゃないっていうことを、自分自身、常に考えていたいですね」。
![]()
本インタビューは、金融広報中央委員会発行の広報誌「くらし塾 きんゆう塾」vol.66 2023年秋号から転載しています。