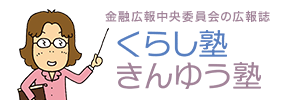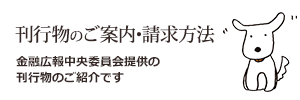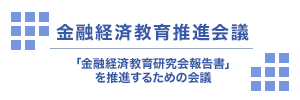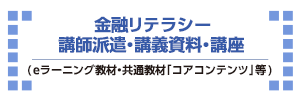著名人・有識者が語る ~インタビュー~
正解はひとつではない 大切なのは学び続ける心
宇宙飛行士 山崎 直子
日本で二人目の女性宇宙飛行士として宇宙に飛び立った山崎直子さん。
現在は内閣府宇宙政策委員会委員をはじめ、宇宙教育のアドバイザーとして宇宙をより身近にする活動を続けています。
今回は宇宙飛行士や母、そして働く女性の視点から幸福感やお金観、さらに人生の試練に立ち向かうヒントをうかがいました。

山崎 直子
(やまざき・なおこ)
1970年千葉県松戸市生まれ。1999年に国際宇宙ステーション(ISS)の宇宙飛行士候補者に選ばれ、2001年に認定。2004年にソユーズ宇宙船運航技術者、2006年にスペースシャトル搭乗運用技術者の資格を取得。2010年4月、スペースシャトル・ディスカバリー号で宇宙へ。ISS組立補給ミッションSTS-131に従事した。2011年8月にJAXAを退職。現在は、内閣府宇宙政策委員会委員、日本宇宙少年団(YAC)アドバイザー、千葉市科学アドバイザーなどを務め、宇宙開発、研究に携わっている。著書に、「宇宙飛行士になる勉強法」(中央公論新社)、「何とかなるさ」(サンマーク出版)、「瑠璃色の星」(世界文化社)、「夢をつなぐ」(角川書店)など。
宇宙飛行士になろう そう意識し始めた中学時代

「宇宙飛行士」という言葉を聞くと、子どものようにワクワクしたり、ドキドキしたり、思わずスーパーマンのような人物を想像してしまったりするのではないだろうか。
「こんにちは」という爽やかな挨拶とともに山崎直子さんが取材場所に現れた。時速2万キロという桁はずれの速度で大気圏を飛び出し、宇宙空間でいくつもの重要な任務を成し遂げた人物が目の前にいる。
しかし、その第一印象はごく普通の女性であることに驚く。そして穏やかで優しい話しぶりにその場の緊張はあっという間にほぐれた。
まずはどんな少女だったのかをうかがった。
「どちらかというと、のんびりとした女の子でした。幼いころから自然と接するのが好きで、星空をずっと見ていても飽きませんでした。生き物にも興味があり、夏の夜にはセミの幼虫が羽化する瞬間を観察したくて毛布に包まってじっと待ったこともありました。宇宙への関心が高まったのは小学校2年のとき。星を観る会で初めて天体望遠鏡を覗いたころからでしょうか」と山崎さんは話す。
その後もプラネタリウムに通ったりする中で、自然と宇宙に興味を持っていった。ただ職業としては、学校の教師やお花屋さんになりたいとも思っていて、いろいろな職業に憧れを持つ他の子どもたちと変わらなかったと山崎さんは振り返る。
ところがある日を境に宇宙飛行士になろうと強く思うようになる。1986年1月28日、中学生の山崎さんはスペースシャトルチャレンジャー号の打ち上げをテレビで観た。
メンバーの一人にはクリスタ・マコーリフさんという女性の高校教師がおり、宇宙から授業を行うことも話題になっていた。しかし、打ち上げから1分ほどでチャレンジャー号は空中爆発という悲劇に見舞われる。
その事故のニュースを見て山崎さんは大きなショックを受ける。憧れである宇宙飛行士と教師の両方の顔を持つその女性の命が、事故によって一瞬にして奪われたからだ。このとき山崎さんは、クリスタ・マコーリフさんをはじめ、空中爆発で亡くなった人たちの意志を、自分が宇宙飛行士になることで受け継げたらと思う。
宇宙へ行く その長い道のりを諦めなかった
高校、大学と進む中で、進路に迷う時もあったが、山崎さんは宇宙飛行士への夢を忘れることなく、まずは宇宙船を開発しようと、大学と大学院で航空工学や宇宙工学を学び、宇宙開発事業団=NASDA(現在の宇宙航空研究開発機構=JAXA)に就職。エンジニアとして国際宇宙ステーションの開発に取り組む日々が続いた。その中である日、山崎さんは宇宙飛行士の募集があることを知り、迷わず応募する。過去にアメリカ留学中に応募をしたときは、選考から外れた経緯があったが、1999年、二度目の応募で見事に宇宙飛行士候補者として選ばれる。
「応募の際には家族からのメッセージを記入する欄があったのですが、父も母も応援する旨を書いてくれました。その頃はまだ冗談だと思っていたのかもしれませんが、嬉しかったのを覚えています。しかし、そこから宇宙への道のりはとても長かったのです」と山崎さんは話す。
念願の宇宙飛行士に選ばれたからといって、すぐに宇宙に飛び立てるというわけではない。日本は有人の宇宙船を持っていないため、アメリカやロシアの宇宙船で行くしかない。だが、いつ打ち上げになるかは未定だった。選ばれてから飛ぶまでの間は宇宙飛行士としての訓練をしっかり受けなければならない。訓練では座学をはじめ、技術面でのトレーニングや緊急時における対応などさまざまなメニューがあった。また、国際宇宙ステーションを支える地上業務も重要な任務であった。この間、山崎さんはアメリカのスペースシャトルだけでなくロシアの宇宙船ソユーズに搭乗できるライセンスも取得した。
しかしゴールはまだ見えない。2003年にはコロンビア号の事故(地球への帰還途中に大気圏で空中分解)があり、スペースシャトル計画自体がストップしていたことも影響していた。つまり、いつ飛べるかが分からないゴールのない訓練だったのだ。そんな当時を山崎さんは「目隠しをしてマラソンをするようなもの」と思い返す。それでも山崎さんは機会を待った。もちろん焦りはあったが、その中で山崎さんは訓練自体に楽しさを感じ、より集中していくようになる。
「どんな道を歩むかは、環境や周囲の要因も影響します。けれども、その道をどう歩くかは、自分で決められます。ですから、どの道を歩くかよりも、どのように歩むかがより大切になってくると思います。『自分ではどうしようもないことに悩むのではなく、今の自分に何ができるのかを問い、決断していくようにしよう』いつしか私はそう思うようになっていました。私は11年間待ち続ける中でそのことを学んだのです」と山崎さんは話す。
宇宙滞在で知った相対的な視点とチームワークの大切さ
そして2010年4月、とうとう宇宙へ旅立つ日がやって来た。
「宇宙飛行士たちは、打ち上げ3時間前からスペースシャトルのディスカバリー号に乗り込み、待機していました。直前まで何があるか分かりません。まだ記憶に新しい日本のイプシロンロケットのように秒読み段階で中止になることもあります。待っている間、メンバーたちと『今日は飛ぶといいね』などと会話していたことを覚えています」と山崎さんは振り返る。

秒読みが終了。すさまじい轟音とともにロケットは大地を後にする。やっと飛べた!そんな感動が体全身にみなぎってきた。しかし、感傷にひたる余裕はなかったと山崎さんは言う。地上から高度400kmの宇宙に到達するまではわずか8分30秒。その間、飛行状況の把握に追われ、気がつけば宇宙に飛び出していたというのが現実だった。けれども、山崎さんは次の瞬間に感動で全身が包まれたと言う。
「それは船内が無重力状態になったときのことです。体がふわっと浮き上がっていきました。同時に塵や埃までもが宙に浮き、それらが光に照らされて美しく輝いて見えたのです。とうとう宇宙に来たという感激と感謝とともに、表現しがたい懐かしさを覚えました。もしかすると無重力は、記憶の奥にある母の胎内にいたころの遠い記憶を思い出させたのかもしれません」と山崎さんは話す。
そんな感動で幕が開けた宇宙生活で、山崎さんは数多くの任務を遂行していく。特に印象に残っているのは、ディスカバリー号で運んできた多目的補給モジュールを、ロボットアームを使って国際宇宙ステーションに接続する作業だった。
取りつける『レオナルド』というモジュールはイタリア製。ロボットアームはカナダで作られている。そして作業は国際宇宙ステーションにある『デスティニー』というアメリカの実験棟で行われ、任務の責任者は日本人の山崎さんだった。
そこには異なる国と国とが協力しあう素晴らしい調和があった。作業の一つひとつが、人と人が互いに尊重する連携プレーがなければできないものだった。宇宙飛行士といえばスーパーエリートを想像するかもしれないが、宇宙という過酷な状況下の活動で最も大切なのは一人のずば抜けた能力ではなく、みんなで力を合わせるチームワークだった。そして、陰から支えてくれている地上管制官や家族の力も忘れてはならない。
もう一つ山崎さんが宇宙で気づいたのは、地球で絶対だと思っているものが宇宙では違うということだ。
例えば空を飛べば、地面は自分の下にあるということを私たちは絶対と思っている。しかし、宇宙では、自分たちの頭上で地球を眺めることもあった。地球を基準にした上と下という概念は宇宙にはない。それと同じように考え方やものの見方も「絶対」という軸から自由になることで、さまざまに広がっていくのではないかと山崎さんは言う。
正解は一つではない
宇宙から帰還後、より宇宙を身近に感じてもらうための幅広い活動を開始し、現在は内閣府宇宙政策委員会委員や宇宙教育のアドバイザーを務める山崎さん。人々と宇宙を結ぶその活動は、多忙を極める。しかしそうした中でも、母親として子どもたちへの教育は大事にしている。
お金に関する教育もそうだ。山崎さんは子どもたちに、お小遣いではなく、何かの働きをしたお礼として、また必要なものを買う際には、それをどう活かすかなどを話し合って、お金を渡すようにしている。
例えば本が好きな長女には読書感想文を書かせ、その内容がしっかりしていればまた本を買うためのお金を渡すようにしているとのことだ。自身が子どものときから受けた教育もそうだった。
単にお金を渡されるだけではなく、何を買うか、何に使うかという目的を持つ習慣をつけることができたと言う。しかし、これはあくまで山崎家のやり方であり、子育ての正解は人それぞれにあると山崎さんは話す。
働く一人の女性として仕事と生活を両立させ、充実した人生を歩むためのワーク・ライフ・バランスについてもうかがった。
山崎さんは「自分はあまりできていなかった」と答えながらも、一人ひとりのペースを考えて、そこから自分に合った仕事と暮らしのバランスを見つけていくものだと考える。また、特に女性は、出産や子育てなどで一時的に仕事から離れることで不安や焦りを感じる場合もあるかもしれない。そういった場合でも、短期的でなく長い目で見ると、仕事以外の経験や視点を持てることで、その後の仕事や人生に役立つことは多いのではないかと言う。
「正解は一つではないということを、私は実際の宇宙生活で実感しました。宇宙に行く前にはあらゆる想定外の事態に対する訓練を受けてきましたが、実際に宇宙では訓練していないことに限ってよく起こるのです。同じように人生においても『こうなるはず』や『こうでなければならない』という考えに縛られる必要はなく、答えは決して一つではないことがたくさんあります。人生はよく道に例えられますが、生きていく上では、真っすぐな道ばかりを歩めるわけではなく、回り道をしなければならないときもあります。むしろ回り道で苦労したほうが経験値は増えてくるはずです。その中で大事なのは、学び続ける心を持つこと。そして、試練に直面したときこそ『成長するチャンス。きっと何とかなるさ』という楽観的ともいえる気持ちになれることが大事だと思うのです。まさに『人事を尽して天命を待つ』ことで新たな答えがきっと見えてくるはずです」と山崎さん。
その穏やかな笑顔の奥には、夢を次につなげていこうという、前を向いて生きる力がみなぎっていた。
![]()
本インタビューは、金融広報中央委員会発行の広報誌「くらし塾 きんゆう塾」Vol.27 2014年冬号から転載しています。