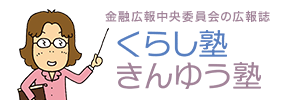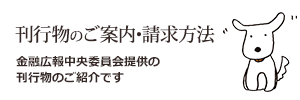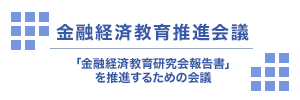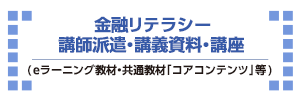著名人・有識者が語る ~インタビュー~
手間をかければ結果につながる。役づくりの労力は惜しまない
俳優 内野 聖陽
大河ドラマ『風林火山』で演じた軍師・山本勘助や『真田丸』の徳川家康、ドラマ『JIN-仁-』の坂本龍馬や『臨場』の検視官・倉石義男など、豪快で破天荒な人物から繊細さを秘めた役柄まで巧みに演じる俳優・内野聖陽さん。
徹底的に役と向き合う真摯な姿勢や仕事観、人生観について、熱く語っていただきました。

内野 聖陽
(うちの・せいよう)
1968年生まれ。神奈川県出身。早稲田大学政治経済学部卒業。大学在学中、英語サークルで英語劇の舞台に立つ。1996年、朝の連続テレビ小説『ふたりっ子』で注目を集め、舞台『みみず』、『カストリエレジー』などの演技が評価され、1998年に紀伊國屋演劇賞個人賞、1999年には読売演劇大賞最優秀男優賞を受賞。2006年には舞台『ベガーズ・オペラ』、『エリザベート』で菊田一夫演劇賞を受賞。ドラマ『風林火山』、『JIN-仁-』、『臨場』、『ブラックペアン』、映画『海難1890』など、多数の作品に出演。
大学の英語劇で知った自己表現の面白さ

豪快でワイルドな役どころの多い内野聖陽さんですが、意外にも「子どものころは人見知りで引っ込み思案だった」といいます。「みんなが騒いでいるのを遠巻きに見ているような子どもで、人前で何かをするのは大の苦手でしたから」と内野さん。
芝居に目覚めたのは早稲田大学政治経済学部に入学してからのこと。入部した英語サークルはディベート(弁論)やドラマ(演劇)などの部門に分かれていて、そこで内野さんはドラマを選択します。
「たまたま英語で芝居をすることになったのですが、やってみたら先輩に『なかなか面白い』と見込まれて、それで味を占めてしまった(笑)。今考えてみると、自分の中に自己表現をしたい強い欲求があったのだと思います。実家はお寺で、そのままいけば父のあとを継いで住職になるはずでした。でも、思春期になって自我が芽生えると、『自分は本当は何がしたいのだろう』と悶々と悩むようになります。そんな気持ちを抱えたまま大学生になって、たまたま英語劇で自己表現をする機会を得た。とくに芝居がやりたかったわけではなくて、ダンスでも書道でも絵画でも、表現ができればなんでもよかったのだと思います。自分の中に溜め込んでいるエネルギーを噴出させる場が、たまたま演技だったのです」。
やがて、大学の先輩から勧められて、数々の名優を輩出する劇団、文学座の附属演劇研究所の門を叩くことになります。
朝ドラで人気俳優へ そして、父への思い
文学座で演技の勉強をしながら、1993年、内野さんはドラマ『街角』に主演します。
「これが僕の実質的なデビュー作です。著名な俳優を一切使わず、駆け出しの役者ばかりを使うという趣旨の作品だったので、監督には現場でずいぶんしごかれました。あのときはかなり悔しい思いもしましたが、叱咤激励してくださった監督は今でも僕の大切な恩師です。劇団文学座で学んだこともたくさんありますが、僕の場合、どちらかといえば現場で揉まれながら鍛えられていった感じでしたね」。
内野さんの存在を広く世間に知らしめたのが、1996年放映の朝の連続テレビ小説『ふたりっ子』です。主人公のライバルとなる将棋棋士で、のちに結婚相手となる重要な役どころを演じ大きな注目を集めました。
「そのときは部屋がいっぱいになるくらいファンレターが届きました。あらためて朝ドラの影響力はすごいな」と驚いたそうですが、人気者になっていくことよりも、内野さんには気になっていることがありました。
「寺を継いでほしいという父の期待に背いて役者の道に進んでしまったので、『役者としてやっていける』ということをいち早く父に証明したかったのです。そういう意味でも、朝ドラに出演できたことの意味は大きかった。父には、僕が想像する以上の絶望感を与えてしまったと思っています。自分が役者になったことで、父をはじめ多くの人たちを裏切ってしまったという気持ちは今でもあります。だからこそ、中途半端なことはできないという意識が常にありますね」。
1998年に紀伊國屋演劇賞の個人賞、1999年には読売演劇大賞の最優秀男優賞を立て続けに受賞したとき、内野さんはその賞金を持って父親に会いに行きました。「もともと口数の多い人ではないし、とくにほめてくれたわけではなかった」そうですが、内野さんが俳優として高く評価されたことを、きっと誰よりも喜び、認めていたであろうことは想像に難くありません。
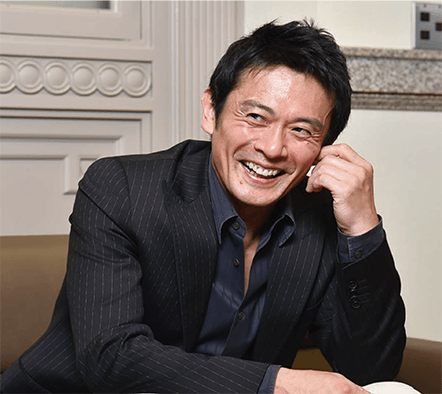
仕事に対しては慎重派 事前の準備は怠らない
俳優として順風満帆にキャリアを積み重ね、怖いものなしのように見える内野さんですが、仕事に対しては「慎重派」だと自己分析します。「負けたくない、失敗したくないという気持ちが強いので、現場に入る前にさまざまなケースを想定して考え過ぎてしまうところもあります。大河ドラマ『真田丸』で、脚本を手がけた三谷幸喜さんは徳川家康をかなりの慎重派として描かれましたが、あれは僕の性分を三谷さんが見抜いて役どころに反映させたのではないかと思っています。
現場に入ってしまえば、『やるしかない』という気持ちで突き進むのですが、とにかく事前にできることはすべて準備しておかないと怖い。例えば、大河ドラマ『風林火山』で山本勘助を演じたときも、脚本にはただ1行「走る馬上で死んだふりをした勘助がやおら起き上がり弓を射る」と書かれていただけでしたが、何百回と馬に乗って弓を射る練習をしたうえで、撮影に臨みました。実在の人物を演じる際は、資料を徹底的に調べ尽くして、自分なりの人物像を構築していきます。
僕らの仕事は、手間や時間をかけた分だけ結果に反映されます。僕は、器用か不器用かでいえば確実に不器用な人間です。器用な人が簡単にできることでも、かなり努力をしないとできないという自覚があります。だからこそ、手間と時間を惜しまずに取り組むしかないのです」。
内野さんのこうした取り組み姿勢は、ドラマ『JIN-仁-』の坂本龍馬役でも顕著でした。
「演じるからには、龍馬の故郷・高知に行かなければと思って、何度も自費で現地に足を運びました。僕は役づくりに関する自分への投資は惜しまないのです(笑)。高知弁が飛び交う夜の酒場で耳をそば立てていたら、あるとき、『内野さんですよね?』と気づかれてしまい、そこからは『この言葉はどう発音するんですか?』などと質問しながら地元の人たちと仲良くなりました。うれしかったのは、地元の人たちが僕の演じた龍馬を見て、『高知出身ではないのに、あんなにリアルに高知弁をしゃべってくれるなんて』といってくださったこと。方言はその土地に根づいた文化です。よそ者がその文化を自分の体の中に取り入れるのは簡単なことではありません。その苦労が報われたような気がして、とてもうれしかったですね」。
私たちは歴史上の人物について、文献などでその功績を知ることはできます。しかし、生身の俳優がその人物を目の前で演じることによって、聴衆は、その時代に生きた人たちの息吹をよりリアルに感じることができます。
「ヒリヒリするような、ときにはゾッとするような人間の生々しさをいかにリアルに表現し見せられるのかが、役者にとっていちばん大事な使命だと僕は思っています。中途半端な芝居を見るぐらいであれば、本や漫画を読んだほうが想像が膨らみます。実写でやる以上、生身の役者が持つ説得力を限界まで発揮すべきです」。
テレビや映画でさまざまな役を演じる一方で、内野さんは毎年のように舞台にも立ち続けています。そこには「舞台が自分の原点」との思いがあるからといいます。
「舞台には、テレビや映画にはないライブならではの興奮や熱狂があります。もちろん舞台にも演出家がいて、稽古で芝居を演出されるわけですが、ひとたび幕が上がってしまえば、幕が下りるまでは役者の力量に任される部分が大きい。役者の放つ熱が見る人の人生を変えるほどの影響力を持つこともあるし、役者自身も自分が思ってもいなかった高いレベルの芝居ができることだってある。その日、その瞬間にしか生まれないものが舞台にはあり、そういう瞬間に出会えたお客さんはラッキーですし、演じられた役者もラッキーです。役者は舞台を捨てたら終わりだという気がしますね」。
何度舞台に立っても、「初日の開演のベルが鳴る瞬間は今でもすごく震える」という内野さん。「でも、その身が引き締まるような緊張感が舞台のよさでもあり、それだけ集中するからこそいいものができる。寿命は縮まるかもしれませんが(笑)」。
「自分で想定できるようなものは大したものではなく、想定外のものが出てこなければ面白くない。そこまで自分を追い込んで舞台を作っていきたいですし、お客さんも役者が命がけで取り組んでいる姿を見たいと思っているはず。そのためには役者がどれだけ苦しむかが大事なのです」。
自分を追い込み 新たな挑戦を続ける
ストイックに自分を追い込み、演技に挑む内野さんですが、仕事と仕事の合間の休みには、なるべく演技のことは忘れて過ごすようにしているのだとか。「1人でフラッと海外旅行に行くこともありますし、違う業界の人と会うことも多いですね。お酒を飲むのは好きなのですが、今は次の作品のために一切やめています。この仕事は、のんびりする時期と緊迫する時期との差が激しいんですよ。僕は『戦争と平和』と呼んでいるんですが(笑)、今は戦闘モードに入っています」。
2018年9月に50歳を迎え、大人の男の色気や哀感を醸し出す俳優として演じる役柄もますます広がりそうですが、ご自身は「50歳だからこういう役を演じたいといった思いはない」といいます。「役者の仕事というのはご縁だと思います。いくら自分はこんな役をやりたいといっても、作り手側が『この役は合わない』とか『まだ早い』、『もう遅い』と判断するものです。その時々、お声がかかったご縁のある役に対して、求められている以上のものにして表現する。役者の仕事は、一つひとつが次の通行手形みたいなものだと思います。一つひとつ真剣勝負でやっていかなければ、次はないのです」。
とはいえ、「40代後半と50歳とでは、気持ちとしてはかなり違う」そうです。「50歳になって、どこか吹っ切れた気がしますね。おじさんとして図々しくいこうかなと思いますし(笑)、これからはくたびれた役もできるかなと思っています。常に変化球を投げたいというか、違う自分を見てみたいという欲望が強いので、今まで演じたことのない役、自分から遠いと思える役があれば、なるべくならそちらを演じてみたい。
役者の仕事は芸術に近いものだと思われがちです。芸術に勝ち負けはないという考え方もありますが、負けたくないという闘争心を持っていたほうが絶対にクオリティが上がっていきます。共演者に自分よりうまい役者がいれば、絶対に負けられないと思う。激しいバトルがあったほうが監督や演出家も喜ぶし、結果として見る人にとっても面白いものになるはずです。若いころと違い、周りからあれこれいってもらえなくなりますから、自分で自分のハードルを高くしていくしかない。だから、『ここまでやらなければ、この先の役者人生はない』、『ここで自分の思う表現ができなかったらあとはない』という追い込み方をしてしまうのです。その姿勢は、これからも変わらないと思います」。
どんな役に対してもとことん真摯に向き合う内野さん。これからも私たちにさまざまな人間のリアルな生きざまを見せてくれることでしょう。
![]()
本インタビューは、金融広報中央委員会発行の広報誌「くらし塾 きんゆう塾」vol.48 2019年春号から転載しています。