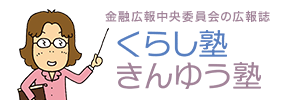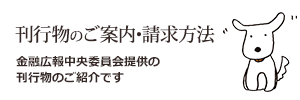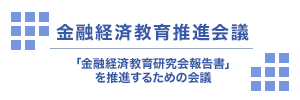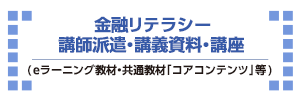著名人・有識者が語る ~インタビュー~
試練を乗り越え生きる力をつくる
明治大学文学部教授 齋藤 孝
新しい教育スタイルを提唱する教育学者として大学やセミナーなどで人材の育成に取り組む齋藤孝さん。
その理論や指導方法は「齋藤メソッド」として知られ、教育界だけに留まらず、ビジネスの現場や家庭にまで支持が広がっています。
今回は、研究や指導、さらにテレビ番組での解説や著作活動にエネルギッシュに取り組む齋藤さんに、幸福感やお金観、そして有意義に人生を過ごすヒントを伺いました。

齋藤 孝
(さいとう・たかし)
1960年静岡生まれ。東京大学法学部卒業。同大学院教育学研究科博士課程を経て現職。『身体感覚を取り戻す』で新潮学芸賞受賞。2001年に出した『声に出して読みたい日本語』がシリーズ260万部のベストセラーになり日本語ブームをつくった。著書に『読書力』『コミュニケーション力』『質問力』『古典力』『現代語訳学問のすすめ』など多数。TBSテレビ「情報7days ニュースキャスター」などテレビ出演多数。NHK Eテレ「にほんごであそぼ」総合指導。
身体のエネルギーの不思議さに気づいた少年時代

取材先に登場した齋藤孝さん。テレビで見かける穏やかな笑顔と口調は変わらない。その上で実際に会うと教育学者として若い世代を育てる思いの深さがやさしい眼差しから伝わってきた。そんな齋藤さんがまず話してくれたのは、少年時代に楽しんだ子ども相撲だった。
「商店街が主催していた子どもの相撲大会が好きで、よく出場しました。結構強かったですよ。土俵も大人たちの手作りで本格的だった記憶があります。もちろん、出場する少年たちも一生懸命でしたが、それを支える大人たちもエネルギッシュでした。地域ぐるみで大会を盛り上げ、子どもたちを元気に育てようというパワーがみなぎっていたように思います」
相撲と一緒に今も齋藤さんの脳裏に鮮明に焼き付いているのは、そのころの人々から発せられていた活力だ。先生をはじめ、接する大人たちの多くがエネルギーにあふれ、その活気を肌で感じながら齋藤さんは育った。その中で元気いっぱいに体を動かすことが自然と好きになっていった。
時代はテレビのアニメでもスポーツものが人気を博し、根性で厳しい試練を越えていくいわゆる“スポ根”に当時の子どもたちは魅せられていた。
齋藤さんもその一人だった。そういったアニメのヒーローたちの影響を受けた当時の子どもたちの間で流行していたのは“特訓”。それは友だちに知られず、練習を積み重ねることで遊びの技を磨くことだった。その中で子どもたちは厳しいと感じる練習量を自分に課し、根性で挑む自分をヒーローたちと重ねていたに違いない。同時にそんな特訓をやり遂げる充実感を、子どもながらに齋藤さんは心身全体で感じていった。学校のクラブ活動も運動部に所属し、日が暮れるまで汗を流し続けた齋藤さん。しかし、受験の学年を迎えて、クラブを引退してから空虚感が少しずつ広がっていった。もうクラブ活動に時間を割かれることのない生活。本来なら今まで以上に受験勉強に集中できるはずだ。けれど齋藤さんは違っていた。
ただ机に向かって勉強するだけの毎日。その繰り返しの中で日に日に気が滅入っていく……。やがて齋藤さんは原因に気づいた。それは今までのように思う存分身体を動かせないからだった。そのストレスに苦しみながら齋藤さんは身体を動かすことが心や思考と深い関係があることを痛感していく。この経験が後に身体を基盤にした教育法である「齋藤メソッド」の構築のひとつのきっかけとなっていく。
貧しさの経験で気づいたお金を得るためのシステム
やがて齋藤さんは大学、そして大学院に進む。しかし、それはお世辞にも優雅な学生生活ではなく、逆に人生で初めて貧しさを体験した時代だったと振り返る。
「大学院のときに結婚していました。けれど立場的にはまだ学生。定職に就いているわけではなかったので安定した収入はありませんでした。だから生活はいつもギリギリの状態。住まいも家賃の安い狭くて古いアパートです。部屋でネズミを見たこともありましたね」と齋藤さんは笑う。
生活は苦しかったが、けっして悲嘆に暮れることはなかった。逆にそういった貧困生活の中で齋藤さんは学問を極めたいという情熱を燃やしていく。
知識を吸収したいというエネルギーは大学院で学ぶだけでは満たされず、齋藤さんはよく深夜のファミリーレストランにも出かけたという。空調が効き、コーヒーが飲み放題のその場所は、当時の齋藤さんにとっては格好の勉強場所だった。
そんなある日、齋藤さんは大学の同窓生たちと食事をした。同窓生たちは企業や組織の中で活躍し、日本の将来や世界経済の動向について論じあっていた。その姿に齋藤さんは自分とは違う大人を感じる。今は学問を極める修業期間と決めていた自分にとって収入面の差に引け目はなかった。しかし、彼らと比較し、決定的なある違いを齋藤さんは感じる。それは、自分がお金を得るシステムにマッチした方法論を持っているか、否かだった。
同窓生たちは、職場で組織が求めている能力を出すことで評価を獲得している。つまり仕事というシステムに適応している。だから収入を得ている。
では自分はどうだろうか、と齋藤さんは自らに問う。今、大学院生として一つのテーマに沿って研究し、論文にまとめている。それは自分が研究したい内容だ。しかし、それを仕事というシステムで捉えたときに、働いている彼らと大きな落差があることが分かった。そして齋藤さんは教育学者として生きていくためには、自分の能力を「やりたいこと」と「社会が求めていること」のバランスが取れた状態で使っていかなければならないことに気づいた。このときの気づきは、齋藤さんにとって大きな財産となる。2001年のベストセラーとなった『声に出して読みたい日本語』などの著作もその視点から生まれた。
子どもたちに自信とエネルギーをつける教育を実践
その後、齋藤さんは大学の教員として学生たちを指導する立場に就く。そこで接するのは素直でまじめに勉強する学生たちだ。その姿勢はけっして悪いものではない。しかし、そこで齋藤さんが感じるのは、若者たちの自信のなさだった。それは大学生に限ることではなく、齋藤さんが主宰している塾に来る子どもたちの多くにも共通するものがあった。
「なぜ子どもや若者たちは自信が持てないのか、ある日から自分の少年時代と比較しながら考えるようになったのです。そこで得られた結論は、心に核となる芯があるか、ないかでした。私たちのころは、“根性”という言葉がよく使われていました。目標に向かって根性でやり抜く。それが美徳だった時代です。子どものころに流行った“特訓”も“根性”が基本でした。そして自分で高いハードルを決め、それを達成するために歯を食いしばってがんばり抜く中で形成されていったのが『心の芯』です。『芯』があるから心が折れないのだ、という自信が持てたのだと思います」と齋藤さんは話す。

それに比べて今の世代はどうだろうか。「叱るよりも褒めて伸ばすこと」が教育の現場で推奨されるようになった。確かにそれは一定の成果を得るかもしれない。しかし齋藤さんは、ただ褒めるだけというのは、子どもたちの能力を低く見積もることにつながるのではないかと危惧する。褒めることでつく自信がある。けれどそれよりももっと大きいのは、自らが試練を乗り越えることで得られる自信で、それは誰か他の人から与えられるものではない。ある日、齋藤さんは子ども講習会を企画した。夏目漱石の『坊っちゃん』を声を出して読み切るというものだ。それはまさに読書というマラソンだった。スタートしてからしばらくすると子どもたちの間からブーイングの嵐が起こる。『坊っちゃん』を音読で読み切るのは物理的には可能だ。しかし体力的、精神的にそれなりの負担を伴う。「疲れた」「もういやだ」と子どもたちから文句が飛び出す。しかし齋藤さんは動じない。何度も中断するたびに姿勢を直し、深呼吸をさせ、「さあ続けよう」と笑顔で励ましていく。
その音読は数時間にも及んでいく、やがて子どもたちの表情が変わっていく。自分のエネルギーを使って身体全体で『坊っちゃん』を読んでいる充実感を感じているのだ。物語への理解の深さが違ってくることにも子どもたちは気づいていく。もう文句は誰からも出ない。そして延べ6時間で『坊っちゃん』を読了する。もちろん子どもたちは疲れている。しかし、始める前よりも元気になっている。そして何よりの成果は、一冊を完全に音読したという自信だった。このとき、初めて齋藤さんは、子どもたちを褒める。
子どもたちは、この音読を通じて自分の中にあるたくさんの弱さを乗り越えていった。齋藤さんがこの企画を通して子どもたちに味わってほしかったのもここだ。人生で大切なのは、自分のエネルギーで「試練を乗り越えていく」という経験だという。これが芯となり、自信になっていく。
技とスタイルが生きる力をつくる
名作を音読で読破する。一冊の本を一気に読む、しかも音読で読み上げるというボリュームある行為に対する負荷は、特別な状況を子どもたちにつくる。齋藤さんが提唱する教育論には、子どもたちには一見無理と見える「量」が密接な関係を持つ。
「それはスポーツでも同じだと思います。たとえばテニスなら素振りを何回、何時間と決めてやる、その繰り返しによって正しい打ち方という型が身についていく。つまり『量』が『質』に変わるのです。これを私は、『技化(わざか)』と呼んでいます。ここで大切なのは量をどこに設定するかという指導者の見極めです。簡単にできる量ではなく、自分の弱さを乗り越えたと実感できる量ができたとき、技が心身に定着していくのです」と齋藤さんは話す。その考え方は、単に学習だけに留まらず、生き方につながっていく。人は生きていく上でさまざまな困難に出会うだろう。そこで役立つのが技だ。いくつもの試練を乗り越えてきた経験から生まれた技。それを複数持つとき、生きる力になっていくと齋藤さんは話し、その仕組みを一流のアスリートに例える。
「私たちに感動を与えてくれる一流の選手には、磨き抜かれた技がいくつもあります。ひとつひとつが、練習に練習を重ねた結果得られた自信の得意技です。しかし、その上でそういった選手たちが素晴らしいのは、幾つもの技によってその人独自のプレースタイルが形成されているところです。これがあるから一流の選手は勝負に強い。この『技』と『スタイル』の仕組みを人生に置き換えて考えたときに、生きる上で力になってくるものが見えてくるのではないでしょうか。私は経験上、『技』が3つ以上揃ったときに『スタイル』になると考えています」と齋藤さん。
この視点は、齋藤さん自身のお金観にも反映されている。本だけは際限なく買ってくれた両親の影響もあって、貧しい大学院時代も読書にはお金を惜しまなかった齋藤さん。そこに象徴されるようにそのお金の使い方には、自身の成長という目的意識があった。そして事実、そういったお金が注がれた膨大な読書量によって齋藤さんは教育学者として確かな成長を遂げ、独自の思考はさまざまに「技化」し、「齋藤メソッド」というスタイルが生まれた。ややもすると「技」や「スタイル」という言葉は、ノウハウや形式といった表層的な意味に捉えられてしまうかもしれない。しかし齋藤さんが語る2つのキーワードには心身の両面から放たれる生きたエネルギーが貫かれている。
約束の取材終了時間が来た。齋藤さんは颯爽と席を立ち、学生たちが待つ大学へと向かう。その身体には、明るく逞しい活力があふれていた。
![]()
本インタビューは、金融広報中央委員会発行の広報誌「くらし塾 きんゆう塾」Vol.23 2013年冬号から転載しています。