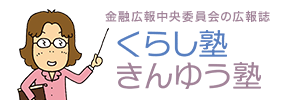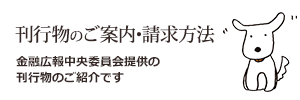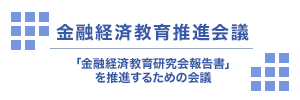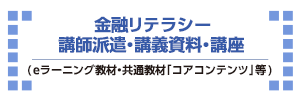著名人・有識者が語る ~インタビュー~
人間とは何かを考え抜く
工学博士 石黒 浩
10 年ほど前、自分そっくりのロボットを創り、世界を驚かせた石黒浩・大阪大学教授。
今ではそのコピーロボット「ジェミノイドHI」が石黒さんに代わって海外で講演を行うなど、 活躍はますます「進化」を遂げています。
2007年には、英国コンサルティング会社(Synectics社)の調査において 「世界の100人の生きている天才」に選出されるなど世界のトップを走るロボット工学者。 その素顔と研究にかける情熱の裏にある人生哲学をうかがいました。

石黒 浩
(いしぐろ・ひろし)
1963年、滋賀県生まれ。大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻教授、 JST ERATO 石黒共生HRIプロジェクト研究総括、ATR石黒浩特別研究所所長(客員)およびATRフェロー。
著書に『ロボットとは何か-人の心を映す鏡』(講談社現代新書)、 『どうすれば「人」を創れるか-アンドロイドになった私』(新潮社)などがある。
絵が好き、創造力を育んだ少年時代
石黒さんの研究テーマは、マンガやアニメで活躍する擬人化したロボット、 あるいは工場などで働く産業用ロボットではなく、 人間と見まがう容姿をしたアンドロイド(人間酷似型ロボット)です。 その研究の目的は、ズバリ、「人間を知るため」。 ロボットを通じて未来の人間社会を支えるシステムを探究し続ける石黒さんの発想の原点はどこにあるのでしょう。
両親・親戚の多くが先生という中で育ったという石黒さん。 いかにも優等生を育む環境だったのかと尋ねると、 意外にも「勉強をした記憶はあまりない」との答えが返ってきました。
「小学校低学年では、まず先生の言うことをきかない子どもでしたね。 授業参観のときでさえ授業を無視して一人で絵を描いていて親に嘆かれたほど。 絵が大好きでしたね」と話すように、石黒さんには幼少期から芸術的な感性が芽生えていたようです。

「3・4年生になると、今度は日記を書くことに熱中するようになりました。 目についたもの、気がついたことを片っ端から書き記すから、 3日でノート1冊がいっぱいになり、2年間でダンボール2つ分になっていました。 そのうち、文章を書くのが楽しくなって、 高学年のころには、先生の話をちゃんと聞くまともな子どもになっていたと思います」。
滋賀県にある故郷の豊かな自然に囲まれ、 「近所の山では野生の松茸、しめじが、川ではアユが採れて、 ご飯のおかずが一通り揃うような環境でした。 カブトムシやクワガタも捕り放題でしたね」と思い出すのは野山を駆け回ったことばかりだそうです。
その後、地元の高校に進み、好きな絵を学ぶために美大へ行くことも考えたものの、 当時普及しはじめていたパソコンにも興味があり、工学部への進学を決めました。
「本当の最先端の研究をするとき、私たちは『何もないところから何かを創り出す』という『発見』が必要で、 いくら論理を突き詰めても『何か』は出てこない。 そこは芸術的なセンス、ひらめきなんです。 そういう意味では、私は子どものころから美術が好きだったことで、 研究者としても役立つ資質を磨くことができたと思います」。
互いに助け合う地域文化に影響を受けた金銭感覚
石黒さんは子どものころ、「おこづかい」をもらわない生活をしていました。
「田舎だから、雑貨屋さんが1つ、八百屋さんが1つ、本屋さんが1つという感じ。 お店の人も親もみんな知り合いで『どこのうちの子か』が分かっているから、 『ツケ(後払い)がきく』という文化が残る地域で育ちました。 だから、現金を持っていなくても買い物ができるけれど、何を買ったかは親に筒抜け、という生活でした」。
もともと手先が器用だったことから、材料と道具さえ揃えば、遊びに必要なものはたいてい作れたと言います。
「おもちゃが欲しいとかではなく、『自分で作るから、材料を手に入れたい』ということなので親もダメだとは言いにくいですよね。 どうしても欲しくて親にお願いした記憶があるのは、『電子ブロック』(1976年に発売されブームになった電気実験キット)と『コンピュータ』ですね。 これはさすがにその辺の材料では作れませんので」。
そんな少年時代の地域のコミュニティは、家に鍵をかける習慣もなく、 個々の家庭同士で足りない物を融通し合って互いに助け合う生活が成り立っていたといいます。 その環境が、石黒さんのお金に対する考え方にも影響していると言います。
「例えば、世の中にお金が生まれた背景には、人とコミュニケーションをとる目的と、 お互いの価値を認め合うプロセスがあったはずです。 しかし今は、お金で物をやりとりするだけになっているのが残念です。 いっそ貨幣制度がなくなれば、人々は『人は互いに助け合って生きている』という本来の姿や、 『人はお金のために働くのではない』ということを思い出すのにと想像したりもします。 お金をなくすわけにはいかないけれど、そうした人間社会の原点に立ち返って考えることが大切です。」 と石黒さんは感じているそうです。
研究とお金についても考え方は明確です。 「もちろん、研究には多額の費用がかかります。 ただ、私には技術開発と実用性の両方を満たせる研究構想が豊富にあるし、 これまでの実験をどんな目的で行ってきたのかも明確に説明できるので、 研究費の獲得には自信があります。 また、自身で経営しているベンチャー企業で研究資金を稼ぐ手もあります。 ただ、この企業は、それ以上に人やアイデアが集まる仕組みづくりという面が大きいですね」。
世界最先端の研究を、話題性も含め、世の中にどのように役立つか分かりやすく説明し、 目標を設定し、成果につなげていく。 そんな“石黒流”に大きな夢と期待が寄せられ、 資金だけでなく人材もアイデアも集まってくると言えそうです。
「人間を知る」ために進化するアンドロイド
石黒さんの代表的な研究成果として、3つのアンドロイドが挙げられます。
1つが2006年に1号機が開発された石黒さん自身のコピーロボットである「ジェミノイドHI」。 次に10年に発表された女性型遠隔操作型アンドロイド「ジェミノイドF」。 そして15年に登場したのが、究極の美形の容姿を持つ自律対話型アンドロイド「ERICA(エリカ)」。
ほかにも、人気タレントのマツコ・デラックスさんのアンドロイドや 大阪の百貨店で販売員として親しまれているアンドロイド・ミナミちゃんなど、さまざまなアンドロイドが活躍しています。
ただ、石黒さんは「私はロボットを作りたいわけではないのです。自分や人間に興味があるから、 人間を知るために、アンドロイドを追究しているのです」と力説します。

例えば、自分そっくりのアンドロイドを製作した理由は、 「人の存在感とはいったい何であるのか、また人の存在感は遠隔地へ伝達することができるか」 といった疑問を探求するための実験だと言います。 「ジェミノイド」にはマイクとスピーカー、通信機能が内蔵され、遠隔操作が可能です。 この機能を活用し、国内外のいろいろな場所で、石黒さんのアンドロイドによる講演会が行われています。 まさに、人の存在感を本人がいない場所に伝達できることを証明した成功例と言えるでしょう。
また、最新型の「ERICA」は、遠隔操作型ではなく、 人間との自然な対話が可能な自律対話型として注目されています。 顔は美人の特徴をコンピューターグラフィックスで合成した「完璧」な造作。 ふるまいは音声認識、音声合成、動作認識、動作生成などにおける最先端の技術を結集して作られているのが特徴です。 実在の人間をモデルとしていない「ERICA」の開発は、姿も声も合成技術の粋を集めて製作されたアンドロイドが、 人間にどれだけ親しまれるかを実験するという、次なるチャレンジなのです。
「人間の脳は人間を認識する能力が一番高く、ロボットに対する反応は人型かそれ以外かで大きく異なります。 人間にとって一番使いやすいのは人間らしいロボットなんです。 つまり、人間にとってもっとも親しみやすいインターフェイス(姿形)は人間なんですよ」。
「人間は道具を使い、技術をもって多種多様なことができるようになり、人間の限界を克服してきました。 技術は世の中を便利にしましたが、人間の能力を機械に置き換えていくと最後には何が残るのか。 人間の能力はどこまで拡張できるのか。 人間の可能性を見続けながら、最後に人間とは何か? 自分とは何か? を見定めることが、私の研究の最終的な目標なのです」。
「私は自身のアンドロイドが遠隔操作中に誰かに触れられたりすると、 自分のことのようにドキドキします。 不意に頬をつつかれたりすると不快な気持ちにもなる。 なんだか境界が曖昧になり、アンドロイドの体験に同化する感覚を持ちます。 自分の体のように感じられてくるのです。 これは、モデルがいる他のアンドロイドの場合でも、 モデルの人からは同じ感想が聞かれました。 同様に、脊髄損傷などで体を動かせない人が、 脳波でアンドロイドを操作すると、 体が動いているような満足感が得られるという実験データもあります。 まさに、『自分』の定義を考えさせられる実験と言えます」。
そして、石黒さんは、「アンドロイドを実体験する感覚をもっと世間一般に広げていきたい」と話します。
テレビ番組で話題となったタレント、マツコ・デラックスさんそっくりの「マツコロイド」。
マツコさん自身、最初は自分そっくりのアンドロイドに「あまりいい気分のものではない」としながらも、 何度か触れ合ううちに自然に会話を楽しむ(遠隔操作で別の人間が対話)ようになっています。 今では完全に独立した人格として認識し、「分身ではないが仕事仲間、妹のような存在」という趣旨の発言もしています。 番組の制作現場でも、スタッフたちは皆、ほとんど一人の人間として接しているそうです。
アンドロイドと人間が実際に接している様子をテレビなどを通じて多くの人に見てもらうことで、 アンドロイドという存在への関心や理解が高まり人間社会に受け入れられることにつなげていきたいとの思いが、 メディア戦略にも込められているのです。
真似は要らない、自分で考える
石黒さんは自身の研究者人生の岐路を、大学院生のころだったと言います。
「大阪大学の大学院で博士号を取る際、死に物狂いで研究テーマを考えました。 人が発想をするときにはひらめきも必要ですが、 それとともに『論理とイマジネーションを完全につなぐトレーニング』が重要です。 そのために1年ぐらい、『答えが見えなかったら死ぬ』というくらいの強い気持ちでとにかく考え続けたんです。 そこまで心理的にも自分を徹底的に追い込みました。 私は幼いころから思い込みが激しい方だったのですが、 自己暗示が得意という意味で、ここでは私の強みとなりました」。
この徹底的に考え抜く日々を重ねるうち、石黒さんは「自分が考えていたバラバラなものが、 あるときにポンと3つぐらい同時につながる直感が働くようになった」と表現しています。
「うまくは説明できないのですが、右脳と左脳がつながった感じがする瞬間があったのです。 それ以来、研究テーマやアイデアは枯渇したことがありません。 さらにその後は、一見嫌なことでも『これは将来のためになる』と確信することで ストレスから解放されるようになりました。 だからもう私にはストレスが一切ありませんね」と言い切ります。
まさにこの博士課程での1年ほどの「考え続ける」体験が、 天才・石黒教授の誕生の布石となり、今日につながっているのかもしれません。
なかなか普通には真似できない石黒さんの方法ですが、 発想力を鍛えるためのアドバイスをうかがうと、 やはり「考え抜くこと」の大切さを思い出話とともに聞かせてくれました。 小学生のころ先生から「人の気持ちも考えろ」と言われ、 素直によく考えてみた石黒少年は「人」も「気持ち」も「考える」ことも、 分からないことだらけなことに気づき、愕然としたそうです。
「新しい世界を切り拓くような研究、 独創的な発想は学校や大人から教わったことを鵜呑みにしていては生まれません。 人のやっていることを真似しても意味はなく、 人のやっていないことをやってこそ成功がある。 まずは、日常の中にある素朴な疑問(基本問題)を分かったつもりにならずに 自分の頭でとことん考え抜く訓練をしてみてください」。
人を知るため、自分を知るために、 数々のアンドロイドを創造し続けている天才ロボット工学者・石黒浩さん。
「究極のところ、人間は人間にしか興味がないんですよ」。 そう繰り返す石黒さんの研究は、将来、人の姿形だけでなく、 「気持ち」や「思い」までアンドロイドに吹き込んでいくことができるのでしょうか? その時、人とロボットの境界線はどうなるのでしょうか? 未来の世界の姿を切り拓く研究からどんな成果が飛び出すのか、私たちも目が離せません。
![]()
本インタビューは、金融広報中央委員会発行の広報誌「くらし塾 きんゆう塾」Vol.34 2015年秋号から転載しています。