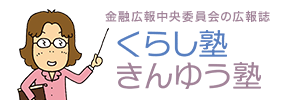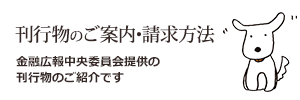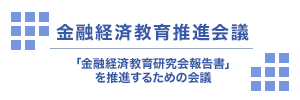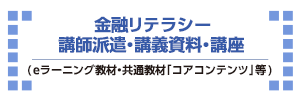著名人・有識者が語る ~インタビュー~
家庭料理の基本である「一汁一菜」で心を豊かに
料理研究家 土井 善晴
和食を基礎とした家庭料理と食文化を探求し続ける料理研究家の土井善晴さん。
日々の食事は、ごはんと具だくさんの味噌汁、漬物などの一菜があれば十分という「一汁一菜」(いちじゅういっさい)のスタイルを提案しています。
そこには、自然や季節のうつろいを感じ取る日本人の美意識が反映されると言います。

土井 善晴
(どい・よしはる)
料理研究家。1957年、大阪生まれ。スイス、フランスでフランス料理を学び、帰国後、大阪「味吉兆」で日本料理を修業。土井勝料理学校講師を経て、1992年に「おいしいもの研究所」を設立。元早稲田大学非常勤講師、学習院女子大学講師。料理番組『おかずのクッキング』『きょうの料理』の講師でも知られ、『一汁一菜でよいという提案』など著書多数。
西欧から帰国後、日本の美を再発見

料理研究家の土井善晴さんは、テレビなどでも活躍した料理研究家・土井勝さんを父に持ちます。父親の仕事ぶりを幼いころから間近で見て育ったこともあり、ごく自然と料理に関心を持つようになったと言います。最初に飛び込んだのはフランス料理の世界。スイス、フランスに留学して本格的なフランス料理を学びました。「和食や洋食というジャンルにとらわれず、料理というものを大きなくくりで捉えたかったので、まずスイスとフランスで学ぶことを自分に課しました」。
フランス料理を学んだ土井さんは、帰国後、日本の美を再発見することになります。
「料理に限らず、自分の身の回りにこれほど細やかで美しいものがあったのかとあらためて驚きました。庭に咲く草花、寄り添うように建つ家並み、母親の煎れてくれるお茶の香りとぬくもり。それまで当たり前だと思って見過ごしていたものが、なんと美しく愛おしいものかと再認識しました。一度西洋の文化にどっぷり浸かったことが、日本の景色や食文化を見つめ直すきっかけになったのかもしれません」。
そして、有名な日本料理店で修業を始めた土井さんでしたが、「最初は、無作為に盛るものとされる漬物の盛り付け方すら分からなかった」と振り返ります。その後、日本料理店での経験をベースに家庭料理を中心に食文化のあり方を考える「おいしいもの研究所」を設立。数々の料理番組や雑誌・書籍などを通じて、「料理をつくること・食べること」の大切さと楽しさを訴えてきました。
「私の強みは、フランス料理から見た日本料理、日本料理から見た家庭料理という具合にさまざまな視点を持ち合わせているところだと思っています。本場でフランス料理を学び、日本料理専門店で和食を学んだうえで家庭料理を見据えることによって、一つの視点にとらわれずに食と向き合うことができた。フランス料理から日本料理が見え、プロの日本料理の世界から家庭料理が見えてくる。プロのつくる日本料理と日常的にお母さんがつくる家庭料理とでは、おのずと料理をつくる視点や動機が異なります。それぞれの良さ、違いを分かったうえで、日本の家庭にふさわしい料理のあり方を提案することが、今の私の仕事では大切になります」。
辿り着いた「一汁一菜」という考え方
戦後の昭和30年ごろ日本にはアメリカ文化がどんどん入ってきて、栄養が足りないからもっとタンパク質をとりましょう、もっと油を使った料理をつくりましょうという風潮が生まれました。日本の食生活は一見豊かになりましたが、その結果、メインディッシュ、つまりおかずから料理を考える文化が広がり、定着していきました。
メディアは常に目新しいごちそう、物珍しいメニューを紹介し、人びとにあこがれを植え付けます。流行に敏感で周りの目を気にしながら生きることの多い現代人にとって、普段からごちそうを食べることが当たり前になってしまいました。
「それを家庭料理にも求めるようになり、家庭のお母さんは毎日ごちそうを食卓に並べなければならないと思い込んでしまう。しかも、これだけ女性の社会進出が盛んになっているにも関わらず、相変わらずその負担を女性だけが背負っているのが実情です」。
土井さんはこうした現状に問題意識を抱いています。もう一度、食の基本に立ち帰る必要があると考え、辿り着いたのが「一汁一菜」という日本の家庭料理の基本型でした。一汁一菜とは、白米や玄米などの主食に味噌汁などの汁物、そこにおかずを一品添えるだけのきわめて簡素な料理を指し、鎌倉時代の禅寺で採り入れられたのが始まりとされます。あるいは、おかずも付かず、ごはんと味噌汁に漬物などの香の物を添えるだけのこともあります。江戸時代の庶民はこうした食事を基本としながら、めでたいことなどがあればそこに魚などを一品添えるという食生活だったといいます。
「一汁一菜」には無意識のうちに自然の美しさが反映される
毎日の食事は、ごはんと具だくさんの味噌汁、そこに漬物などの一菜があれば十分。多彩なおかずをいくつも並べることが当たり前になってしまった日本の食卓に対して、最も簡素な和食の基本ともいえる「一汁一菜でよい」という土井さんの提案は、大きな話題を呼びました。
「私の料理講習会などに集まる若い主婦の方たちから、子育てをしながら食事の支度をするのが大変だという声をよく耳にしていました。毎日おいしいものを何品もつくらなければならないというプレッシャーが強いなか、私の『一汁一菜でよい』という提案にホッとした人も多いようです。これならあれこれ悩まずにつくれますし、野菜などの余った食材は味噌汁の具として使えばいいので食材の無駄も少なくなります」。
いつもごはんに味噌汁、漬物ではつまらないと思う人もいるかもしれませんが、一汁一菜は、たとえ同じようにつくっても、日々おのずと変化していくものだと土井さんは強調します。
「季節によって味噌汁の具は変わりますし、その日の天気によって、『今日はたくあんの切り方を変えてみようか』とか、『今日は体調がすぐれないからごはんをやわらかく炊こう』というように、毎日同じようにしようと思っても、決して同じにはなりません。朝起きて空を見上げるように、季節や自然と対話をしながら、今日はどうしようかと考える。それが料理をつくることの原点であり、食べることの基本です。忙しい日々のなかでつくる一汁一菜であっても、そこには四季のうつろいや自然の美しさが無意識のうちに反映されるのです。自然や自分の体の変化と素直に向き合えば、昨日と今日とではおのずと違う料理になっているはずです」。
とはいえ、何も一汁一菜しか口にしないストイックな暮らしを強いているわけではありません。一汁一菜を基本として、ときにはそこにプラスアルファでおかずを足す楽しみがあっても良いと土井さんは言います。
「今日は人が集まるから、ちょっと手の込んだ料理をつくろうというのも楽しいでしょう。時間と気持ちとお金に余裕があるときは外食してもいい。昔から日本には『ハレ』(特別な状態、祭り事)と『ケ』(日常)という考え方がありますが、毎日『ハレ』にしようと思ったら大変ですし、する必要もないのです。毎日ごちそうを食べる必要はありません。もっといえば、毎日の家庭料理はおいしくなくていいのです。
普段料理をしない人でも、一汁一菜であれば、朝忙しいときでも手早くつくれます。男女年齢を問わず、自分でサッとつくって食べて出かけることも可能です」と土井さんは言います。
「料理、特に和食の場合、形をきれいに整えようとし過ぎると、食材に触れる時間が長くなり、結果的に鮮度が落ちて雑菌も増えます。お刺身でも、手で触れば触るほど熱が加わり鮮度が落ちるため、なるべく食材には触らずに包丁を入れるのが基本です。一汁一菜は、人目を気にする料理ではなく、サッと手早くつくるものなので、食材に触る時間がきわめて短いのも利点です。自分でつくって自分で食べるのであれば、体裁を整える必要もありません。家族につくる場合は、彩りなどに気を付けて具材を選ぶのもいいでしょう」。

きちんとしたものを食べることは、自分を大切にすることにつながる
土井さんが提案する一汁一菜のスタイルは、今さまざまな世代に反響を呼び、広がりを見せているようです。
「みんな健康になりたいという気持ちは強いんですよ。若い人たちも、自分の体を考えると外食ばかりでは良くないことをよく分かっています。こういう人たちはひとたび一汁一菜に触れると、外に出て食べるところを探す方が面倒くさく、一汁一菜を家でつくる方が楽ということに気づくようですね。一汁一菜を実践していると、自分の味覚が敏感になっていくのが分かります。そもそも味噌汁の味噌は微生物がつくり出す複雑な味。毎日食べても、飲んでも飽きないし、いつもおいしいと感じる。舌先だけで味わうのではなく、体に入ってからしみじみと実感するおいしさ、細胞が感じる癒しのようなものと言ってもいいかもしれません。こうしたことに若い人たちも気づき始めているようです。
あるいは、食が細くなった高齢者にとっても、一汁一菜は理にかなっていると思います。人間はやはりいくつになっても体にいいものを食べたいという気持ちがあるものですが、これなら一人暮らしのご高齢の男性でも自分で簡単につくることができます。食というと、どうしても食べることばかりが注目されますが、本当は料理をつくることと食べることはセットで考えるべきなのです。一人暮らしであっても、料理をつくることができれば、人に頼らずに暮らしていける。一汁一菜であれば、料理の仕方を覚えなくてもつくれます。いざとなったら自分でつくれると思えるだけでも安心です。料理をつくることには楽しさがたくさんあるし、実際につくってみることで、さまざまな発見もある。よく土に触れたり、山や海など自然に触れることが大切だといわれますが、料理をつくることは素材という大自然に触れることです。自然を感じ、季節を感じる。手から伝わってくるものはたくさんあります。料理をつくること、きちんとしたものを食べることは、自分をいたわること、大切にすることにつながると思います。ぜひ、料理をつくること・食べることを暮らしの『柱』にしていただきたいですね」。
![]()
本インタビューは、金融広報中央委員会発行の広報誌「くらし塾 きんゆう塾」vol.44 2018年春号から転載しています。