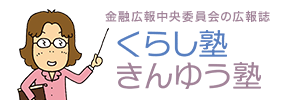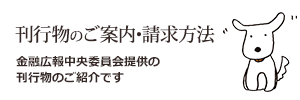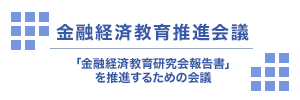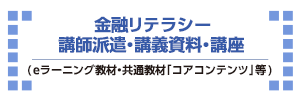著名人・有識者が語る ~インタビュー~
自分を磨く たくましく生きる
作家 荒俣 宏
作家、評論家として多くの著作を著し、精力的に活動する荒俣宏さん。
その活動分野は、幻想文学、図像学、神秘学、博物学と多彩に広がります。
そんな荒俣さんが捉えたお金と人とのかかわり方やたくましく生きるヒントを伺いました。

荒俣 宏
(あらまた・ひろし)
1947年東京生まれ。慶応大学卒業後、10年間のサラリーマン生活ののち独立。神秘学、博物学、風水など多分野にわたり精力的に執筆活動を続け、その著書、訳書は300冊を超える。近著に『新帝都物語』角川書店、『アラマタ大事典』講談社、『アラマタ美術誌』新書館など
実践を通して金銭感覚を身につけた少年時代

もの静かで語り口は穏やか。取材に応じてくれた荒俣さんは、テレビで見るのと同じような印象である。そして、その表情からは芯の強さも伝わってくる。
団塊世代である荒俣さんの少年時代は戦後の復興期。当時は貧しい世帯が多く、荒俣さんの家族も同じだった。
「最近まで言われていた一億総中流といった意識などはその時代にはまったくなく、私のまわりは、みんな生活が苦しかったですね。同じように貧しかったから、それを隠す必要もなかったのです。お金はありませんでしたが悲壮感はなく、むしろ明るかったですね」と荒俣さんは少年時代を振り返る。
友だちの家に遊びに行く。ときにはおやつも出してくれる。それは手作りの素朴なものばかりだ。もちろん荒俣さんの家庭でも同じだ。しかし、今思い出すとそういったおやつ一つを取っても貧しいなりの工夫があったことに気づき、ありがたみを感じるという。
商店を営む暮らしの中で荒俣さんはそろばんを覚え、家業を手伝ううちに自然にわが家の家計状況も把握していった。やがて荒俣さんは『入る』『出る』という、お金には流れがあることも理解していく。
ときには親が銀行などに資金の工面にいくときも一緒に連れて行かれた。銀行とはお金を預けるだけのところではなく、融資してくれる場所であることも日常の暮らしの中で実践として学んでいった。
“得るためには何かをあきらめる“ことを学ぶ
町工場が立ち並ぶ中にもまだ豊かに自然が残っている町で少年時代を過ごした荒俣さんは、野原を駆け回れば昆虫や動植物に、工場のそばで遊べば機械や部品にと、いろいろなものに興味を持ちながら育つ。
また、本に触れる環境として貸本屋の存在が大きかった。そこで借りて読む漫画は荒俣さんの感性を刺激し、視野を広げた。
そんな少年時代を経て、やがて荒俣さんは好奇心旺盛な中学生、高校生へと育っていく。荒俣さんの好奇心と知識欲は枯れることがなく、逆にそれを満たすために図書館の本を読みあさった。ジャンルは文学から歴史、文化、芸術、そして生物や宇宙などありとあらゆる学問の領域に及んだ。中学、高校と昼夜を問わず図書館から借りた本を読み耽ったが、それだけでは知識欲は満たされなかった。もっと本を読みたい。しかし残念なことにお金はなかった。
「私立の中学・高校に通う私のために親は必死で学費を工面してくれていました。ですからそれ以上、お金を欲しいなんて言えません。そこで、通学代と昼食代としてもらっていたお金を浮かして本を買おうと思ったのです。通学はたまたま安く購入した中古の自転車で通うことで解決しましたが、昼食代を本代にあてるのはかなり大変でした。何しろ空腹をがまんするわけですから」
4時間目が終わり、昼休みが始まる。荒俣さんは、教室で弁当を広げるでもなく、また友だちと学食に行くでもない。グラウンドでポツンとただ一人時間が過ぎるのを待つだけである。昼食の時間がある程度過ぎれば昼休みに図書館が開く。荒俣さんはその時間を待った。そして図書館で本を広げればお腹が空いていたことも忘れて読書に没頭できた。そうして浮かせた昼食代は本の購入へと費やすのだった。
そんな荒俣さんを見守っていたのは校長先生だった。
グラウンドから図書館という独自の昼休みのコースの中で荒俣さんと校長先生はまるで読書仲間のように本について語りあう日々が続いた。年齢や教師と生徒という立場を越えて、本という、ともに好きな世界を話題にした会話に荒俣さんは時間を忘れた。
ときには、荒俣さんはこの中高生時代に貯めたお金で高価な洋書も手に入れていく。その中で後の翻訳活動にも生きてくる語学力も身につけていった。
読書によってたくさんの知識を身につけ、感性を磨いていった荒俣さん。その代わりとしてがまんしたのは空腹だけではなかった。中高生といえば思春期の真っ最中。恋愛やおしゃれにも関心はもちろん高まっていくはずだ。
しかし、荒俣さんは興味をあえて持とうとしなかった。
荒俣さんは、それを「あきらめる」という言葉で表現する。何かを手に入れるためには、何かをあきらめる。その大切さを荒俣さんは中学、高校時代に学んだ。あきらめることで湧き上がる悲しさや悔しさが自身の人間形成の上で大きなバネとなり、原動力となっていくことを知った。すさまじい数の著作を生み出す創造のエネルギーも実はそこにあると荒俣さんは語る。
現実を冷静に受け止め、打開策を見つけていく

たくましく育った荒俣さんは、現代人がともすると貧しさに弱い傾向にあることを危惧する。格差という言葉が物語るように、かつての安定した中流意識は揺らぎはじめた。経済的な厳しさに悩む人々は、けっして少なくないだろう。
しかし、と荒俣さんは言葉を続ける。
「お金がないからと言って犯罪に走ったり、自らを傷つけてしまうケースがあまりに多くはないでしょうか。もちろんそれぞれにそうせざるを得ないぐらい、深刻な状況があったのかもしれません。それでも私は、人々が貧しくとも明るくたくましかった自分の少年時代とどうしても比べてしまうのです」
明日の食事代も事欠く貧しさ。その上、自分だけではなく、子どもたちにも食べさせてやらなくてはいけない。そんな切羽詰まった状況でも荒俣さんの家族やまわりの人びとはみんなたくましく生きてきた。
そこには現実を冷静に受け止める目があったと荒俣さんは考える。そして目の前の現実から目をそらさず、しっかり見つめることで、何が可能で何ができないのかがしっかり見えてくる。そこから現実を乗り越えていく打開策をつかんできたのではないかと言うのだ。
荒俣さんは自分の子ども時代を“9歳まではサンタクロースを信じた少年少女“と自嘲する。逆に10歳を過ぎたころには、甘い夢ではなく現実をしっかり受け止める目が自然に養われていたと話す。
「現在のような作家や評論活動を夢みたことはありました。しかし、生活を無視してまでそれを実現しようとは思いませんでした。10歳から養った現実感覚がしっかり身についていたのでしょうね。好きな勉強をしながら安定した仕事に就き、そのまま定年退職しようと思っていたのです。たまたまチャンスに恵まれてデビューはできましたが」
10歳でそろばんを身につけ、自分が置かれている状況を的確に把握した自身の少年時代のように、現実を直視し、打開していく知恵を養えば、極端な行動に走らなくても済むのではないかと荒俣さんは、考える。
お金を使うこと。それは自分へ投資すること
荒俣さんの現代人への目線は、お金と関わるスタイル自体にも向けられる。
物物交換から貨幣へ。そして紙幣、電子マネーへと変化していく人とお金の関わり方。その中で荒俣さんが興味を抱くのは、紙幣の登場だ。元来、金や銀などモノとして価値がある貨幣から、紙幣という“紙に信用を持たせる“といった意識づけの変化に荒俣さんは着目する。
われわれは、確かに物心がついたころから紙でできたお金の価値を信用して育ってきた。そしてそれが当然のことだと思っている。しかし、必ずしもそうではない史実があったことを荒俣さんは教えてくれた。
「明治元年に日本初の全国通用紙幣である太政官札が発行されました。しかし当時、国民は紙幣に不慣れであったため、発行当時は別のものに交換する人々も多く、なかなか流通しませんでした。つまり紙のお金は今とは比べ物にならないほど信用が低かったのです」
さらに太政官札には13年間という通用期限が設けられていたという。お金に使用の期限がある。現代人の生活からは想像し難いことだ。
それでも紙幣が普及し、信用を得ていったのは便利であったからだと荒俣さんは見る。利便性と信頼性という座標軸の間で紙幣は人々の意識の中に完全に定着していった。こうした意識付けがあったからこそ、電子マネーのような、目に見えないデジタル上の価値が思いのほかスムーズに現代社会で受け入れられたのではないかと荒俣さんは推測する。
荒俣さんは今後もよりバーチャル(仮想現実)にお金、そして金融の世界が変化していく可能性を感じている。しかし生活はリアル(現実)だ。仮想現実と現実が交錯する日々の中で、自身の足元を見つめ直し、生きていく上で大切なこととは、何だろうか。
「自分に投資していくことだと思います。それは私のお金に対する考え方でもあるのです。私は、お金は、どう使うか、何に使うか、が大事だと考えてきました。今でも、自分への投資としてお金をどう使うかを常に考えるようにしています」
荒俣さんが言う自分への投資とは、自分を磨くことだ。もちろんそこには知識や教養も含まれるだろう。しかし、それだけではない。大切なのは人生のさまざまな局面で知恵を発揮できる自分をつくり上げることだと荒俣さんは自身の経験から考える。知恵と知識を蓄えて、強く生きていくために自分を磨いていく。時代は変わってもお金はそういった自分への投資のためにあると捉えることが大事ではないだろうか。荒俣さんが静かで穏やかな中にとても強い芯を感じさせるのは、自分を磨き続けるたくましさがあるからに違いない。
![]()
本インタビューは、金融広報中央委員会発行の広報誌「くらし塾 きんゆう塾」Vol.15 2011年冬号から転載しています。