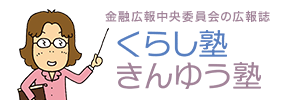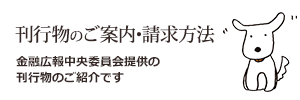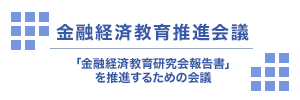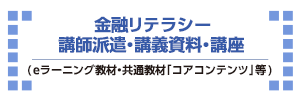著名人・有識者が語る ~インタビュー~
「覚悟」がなければ結果は出ない
青山学院大学陸上競技部監督 原 晋
東京箱根間往復大学駅伝競走(通称:箱根駅伝)で2015年から2年連続総合優勝(2016年は完全優勝)を飾り、圧倒的な強さで脚光を浴びている青山学院大学陸上競技部。
その育ての親が、監督の原晋さんです。選手として箱根駅伝出場の経験はなく、現役引退後監督就任までの10年間は陸上競技からまったく遠ざかっていたという異色の経歴の持ち主。
原さんが語る強いチームの育て方とは?

原 晋
(はら・すすむ)
1967年広島県三原市出身。世羅高校、中京大学を経て、中国電力。04年青山学院大学陸上競技部監督就任。09年箱根駅伝出場。15年、16年箱根駅伝2年連続総合優勝。
ビジネスの経験を生かした「チームづくり」「選手の育成」で陸上界の常識を破り、快進撃を続ける。著書に、『フツーの会社員だった僕が、青山学院大学を箱根駅伝優勝に導いた47の言葉』(アスコム刊)など。
「青学旋風」、箱根路を駆け抜ける

青山学院大学陸上競技部は1918年に創部した伝統あるチームですが、1976年を最後に箱根駅伝からは長らく遠ざかっていました。原さんが監督に就任した2004年当時は専用のグラウンドもなく、雰囲気は体育会の運動部というよりもサークルのようだったといいます。そんななか、陸上競技部の体制を一新し、大学スポーツの花形である箱根駅伝に出場する看板運動部に育てようというプロジェクトが始動。新たな監督に選ばれたのが原さんでした。
監督就任5年目、33年ぶりに予選会を突破して箱根駅伝に出場。その翌年に41年ぶりのシード権を獲得してからは毎年出場を果たし、ついに2015年、2016年と2連覇を成し遂げ「青学旋風」を巻き起こしたのです。
「監督になって最初に取りかかったのは、部員に規則正しい生活をさせることでした。朝5時起床、門限22時、消灯22時15分。駅伝は体ひとつの競技ですから、規則正しい生活が第一。それがベースにあってこそ、練習を重ねて技術を高めていけるのです。ただ、就任後3年間はルール破りが日常茶飯事で本当に大変でした。おまけに大学やOBからも『原は厳しすぎる』と非難されたりしましたからね。しかし、土壌を良質なものに変えなければ、いくら苗を植えても荒れ果てる。そう信じていましたから、根気強く取り組みましたよ。監督というより生活指導部長といった感じでしたね」。
そんな原さんの指導理念やノウハウは、自身の競技経験というよりも、中国電力の営業マン時代に培ったものだといいます。
やり切れずに終わった自身の競技人生
原さんは1967年生まれ。日本の高度経済成長とバブル経済の恩恵にあずかった世代ですが、あまり物欲のない性格だといいます。3人兄弟の末っ子でガキ大将タイプ。友だちを集めては、ルールや戦略を練って遊ぶことが好きで、勝負にこだわる負けん気の強さは人一倍でした。
「広島県三原市にある実家は自宅の窓から釣り糸を垂らすことができるほど海に近く、子どものころはとにかく外遊びに夢中でした。その実家近くの国道2号線が『中国駅伝』のコースになっていて、宗兄弟など実業団の駅伝選手に憧れ、陸上を始めたのです。しかし、中学の陸上部で長距離選手だったのは自分だけでしたね」。
そこで原さんは中学3年のとき、三原市中学校駅伝大会に出るため、テニス部やバスケ部の生徒を誘い、寄せ集めチームをつくります。人集め、チーム編成、区間の人選、レースの戦略まですべて指揮をとり、見事に優勝。自ら組み立てて成果を出す、その成功体験が原さんの駅伝人生の始まりでした。
高校は全国トップレベルの長距離選手が集まる、広島の名門・世羅高校に進学します。
「寮生活は上下関係が厳しくて…。また理不尽なことを要求する先輩たちが嫌で嫌でたまりませんでした。それでも陸上がやりたくて、わざわざ地元を離れてまで選んだ道。何が何でも結果を出そうという覚悟がありました。だから、競技で先輩を見返してやろうと思ったんです」。
自分たちが3年生になると、上の人間の既得権益を守るだけの理不尽なルールは一切廃止しました。
「私はいつでも、みんながハッピーになる選択をします。上下関係にこだわるより、もっと本質を議論し、世羅高校が勝つために、先ざきの予測を立てて今やるべきことを考える、それが大事だと信じていました。際立った選手のいない私たちの学年は監督から『駄馬軍団だ』と言われてね。だから、チームの体制づくりから始め、自分たちでルールを決めて練習に励んだのです」。
原さんは主将としてチームを引っ張ります。その結果、全国高校駅伝大会で準優勝という好成績を残し、陸上競技人生で最大の成功体験を掴むのです。
しかし、その後進学した中京大学、陸上部の1期生として入社した中国電力での成果はいまひとつ奮いません。そして、故障が原因で引退を余儀なくされてしまいます。
「大学時代、1、2年はパチンコと飲み会に明け暮れ、3年で日本インカレ5千メートル3位という結果こそ残したものの、希望した実業団からは門前払い。中国電力では捻挫をきちんと治療せず、監督とは衝突してばかり。結局、大学でも実業団でも覚悟の度合いが足りなかったのだと思います。高校進学のときのように、覚悟を持って自ら選んだ進路ではなく、他人に言われ、なんとなく決めた道ではいけなかったんです」。
選手寿命が尽きて引退するのではなく、半ば追い込まれる形で引退することになった原さんには、どこかやり切れずに終わったという思いが残りました。
営業マンの経験があるからこそ今の自分がある
現役引退後、原さんは中国電力の本店から営業所に配属されます。もはや陸上部員という肩書はなく、入社5年目にして一から仕事を覚える日々。異動のたび小さな営業所に配属され、挫折感を味わいました。そんなときに転機をもたらしたのが、「提案営業」という仕事でした。工場や事業所を回り、夏場の電力供給を効率化してコスト削減につながる提案をするものです。自前の営業マニュアルを作り、提案力と持ち前の性格で信頼を得て、トップクラスの成績を上げます。
この仕事で営業の面白さに目覚め自信をつけた原さんは、社内公募の新商品のプロジェクトに応募しました。新たな販路や営業手法を確立し、社内表彰されるほどの実績を残すのです。
しかし、そこまでであれば、単なるトップセールスマン止まりだったかもしれません。
2000年に中国電力は、新しくできた「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく評価機関として、住宅性能評価を行う新会社設立を決定。原さんはその立ち上げメンバーに選ばれます。ただ、顧客となるはずの住宅メーカーや工務店は「土地さえよければ売れる」といって、自分たちが建築した建物に「住宅性能評価」を行うことに積極的ではなく、最初はまったく実績が上がりませんでした。
「とうとう痺れを切らした社長から5千万円の資本金がどんどん切り崩され2千万円ほどに減ってしまった通帳を突きつけられ、『どうするんじゃこれ。お前のやっとることは所詮我流なんじゃ。基本から叩き直せ!』と一喝されましてね。そこで目が覚めたんですよ」。

営業マンとして「物を売る自信」は持っていましたが、それは中国電力の看板と売れる商品があればこそ。電力事業とは直接関係のない新たな商売において、今までのノウハウだけでは太刀打ちできないことに気づくのです。
「新会社には、第三者機関として住宅性能保証を担うことによって住宅の付加価値を高め、『日本の住宅産業界に貢献する』という大義がありました。その大義を実現するためにどう事業を組み立て、会社を成長させていくか。年間目標を立て、達成プロセスを検討し、社内外の誰を動かすべきかなど、ビジネスの基本を学び直しました」。
この経験があったからこそ「今の自分がある」と原さんは断言します。
目標達成に向けて戦略を練る――こうして原さんは、「カリスマ営業マン」へと進化。地元ファンが熱狂する広島東洋カープの試合中継というゴールデンタイムに、自らラジオCMに出演するなど、アイデア豊富な営業スタイルと戦略、顧客や取引先を巻き込んでチームとしていく人間力で実績を上げていくのです。
そして、サラリーマン生活も10年経ち、新会社を軌道に乗せたころ、ふいに舞い込んできたのが青学陸上競技部の監督就任の話でした。
「世羅高校の後輩に同じ広島で働く青学OBがいました。酒を飲みながら陸上競技の選手指導論について熱く語り合う間柄で、その彼が『原なら』と推してくれたのです。箱根で走った経験も、監督経験もない者が箱根駅伝をめざすチームを率いるなんて異例中の異例です。でも、すべてを一新して箱根に挑戦したいという青学関係者の熱い思いに共感しましたし、旧来型の指導法ではなく、理論に裏打ちされた指導法で箱根をめざしたかった。そして、原は任せたら確実に成果を出す男だと、陸上界でも証明したかった」。
しかし、それは安定した職を捨て、退路を断っての挑戦。原さんの「大きな覚悟」は、反対する家族の心も動かし、いざ東京、箱根路へと向かうのです。
「個の目標」から「チームの目標」へ
箱根駅伝では、青学選手の楽しそうな笑顔が、従来の駅伝選手のストイックなイメージを一新したことは間違いありません。「陸上選手は、これまで『黙々と走れ』という指導を受けてきました。そのため、辛抱強く一つのことをやるのには向いていますが、横のつながりを築いて、他人とコミュニケーションを図っていくのが上手ではない」と原さんは陸上選手の特性をこう捉えます。そこで、こうした欠点を補うようなチームづくりと指導を続けていきます。
その一つが「目標管理ミーティング」です。青学の選手は、例えば「○○大会で○秒記録を伸ばす」というように「個人目標」を設定しています。
「ただ、他人から言われた目標に対しては、選手の意識は希薄になりがちで、実効性が伴わないことが多いのです。だから、各選手に個人目標を立てさせた上で、控え選手なども交えたグループでそれぞれの目標について話し合い、他者の客観的な評価を受けることで達成可能な目標に仕上げていきます」。
選手一人ひとりがこうした「目標管理」によって個のスキルを上げる努力をし、結果として組織のレベルが上がり、「チーム目標」が達成できる。そんな好循環が実現しているといいます。
そして、ここまで強くなったチームの監督の仕事は、「管理することではなく、感じること」だというのが原さん流です。
「私はグラウンドで選手たちに背中を向けていても、走る足音を聞くだけで『どの選手』で『今、どんなコンディション』なのか、ハッキリ区別できますよ。“嗅覚”を研ぎ澄ますことで選手の変化を早目に察知し、事故やトラブルを未然に防ぐ。企業の管理職に求められる危機管理能力と同じです」。
また、小さな成功体験を多く経験させて自信を育み、たとえ「箱根駅伝出場」という目標を達成できなくても、その結果を受け止め、別の道を考えることのできる選手が育っています。
「陸上競技の場合、1番がいれば50番もいます。50番の選手がやはり50番のままでも、自己ベストを出せば必ず褒めます。そして、どう努力をすれば次の結果につながるかを一緒に考え、ヒントを与えています。選手として芽が出なくても、マネージャーとして活躍する選手が現れたり、故障で苦しみ、大会に出場できるかできないかの瀬戸際で、自分が選ばれたい気持ちをグッと我慢して、チームが勝つために辞退を申し出る選手もいます。そんな選手たちと向き合うたび、本当は出してやりたい思いで胸が熱くなりますけどね」。
4年間を走り終えたのち、選手の多くは陸上とは関係のない企業に就職していきます。陸上で培った「一つの目標に向かって諦めない気持ち」を忘れず、新たな道で活躍してほしいと、原さんは一人ひとりの就職活動にもアドバイスをしているそうです。
箱根駅伝で青学陸上競技部が脚光を浴びている今、原監督は青学が起爆剤となり、駅伝だけでなく「陸上競技全体がもっと注目されるスポーツになってほしい」と願っています。
「私は『日本の陸上界を変えたい』という大義を持って青学の監督に就任しました。“原はメディアに出過ぎだ”、“しゃべり過ぎだ”とよく言われますが、駅伝が注目されることで、私のように駅伝に憧れる子どもが現れ、陸上競技人口が増えたり、駅伝を応援する人が増えれば、計り知れない経済効果をもたらすことができるはずです。私は、野球やサッカーのようにスポーツ紙の1面を陸上ニュースが飾り、日本中で陸上を楽しむ人を増やしていきたいのです」。
2020年には東京オリンピックを控え、陸上界にどんな旋風を巻き起こしてくれるのか、原さんのさらなる活躍を期待せずにはいられません。
![]()
本インタビューは、金融広報中央委員会発行の広報誌「くらし塾 きんゆう塾」Vol.37 2016年夏号から転載しています。