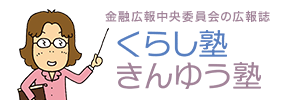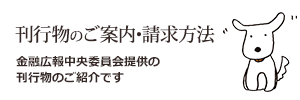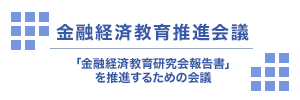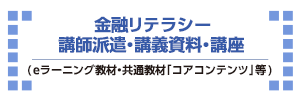著名人・有識者が語る ~インタビュー~
芝居が人生
劇作家・演出家・女優 渡辺 えり
渡辺えりさんといえば、テレビや映画でさまざまな役柄を演じる実力派女優のお一人ですが、23歳のときに劇団を立ち上げて以来、劇作家・演出家としても第一線で活躍してきたことをご存じでしょうか。
現在も、観客に生きる喜びを与える新たな舞台づくりに取り組んでいます。
今回は、「芝居が人生」と語る渡辺えりさんに、プロになろうと決めたときの思い出や、お金にまつわる苦労話、演劇を通して伝えたいことについてうかがいました。

渡辺 えり
(わたなべ・えり)
劇作家・演出家・女優。1955年山形県出身。
企画集団「オフィス3○○(さんじゅうまる)」主宰。
作・演出・俳優として活躍し、一般に向けた私塾「渡辺流演劇塾」では後進の指導にもあたっている。 今秋は都内劇場にて、有吉佐和子原作舞台「三婆」に出演予定。
また、来年初に公演予定の新作書き下ろし舞台「鯨よ!私の手に乗れ」の準備を進めている。
物語の続きが気になって自分で作った

渡辺さんは山形県の出身。村木沢という小さな村で育ちました。夢見がちで物語が大好きな子どもだった、といいます。
「祖母や両親が夜ごと、ふるさとの民話や童話を読み聞かせてくれました。狸に化かされた村人の話とか、現実と夢がまざったようなお話に夢中になって、何度もお話をおねだりしていました。また父が詩人の高村光太郎と宮沢賢治に傾倒していて、私が1、2歳のころから詩や童話を朗読してくれていたようです。もちろん意味なんて分かるわけはないのですが、美しい言葉のリズムがとても心地良かったことを覚えています。言葉が分かるようになると、物語の続きを自分で作るのが楽しくなって。それをみんなに話して聞かせると大喜びしてくれるので、その喜ぶ顔見たさに、あれこれお話を考えていました」。
歌も大好きで、家族の前だけでなく、村のあちこちの家に遊びに行っては覚えたての歌を披露して、食事をごちそうになって帰ってきたりもしたそうです。村全体が大きな家族のようなあたたかい雰囲気のなか、渡辺さんは生き生きと過ごしました。
しかし、5歳で山形市内に引っ越し、小学校に入学した途端に、渡辺さんは思いもかけないいじめに遭います。背も高く体格がよかった渡辺さんに、心ない言葉で意地悪する子が現れたのです。そのため家に引きこもりがちになり、2年間はほとんど不登校に。そんな渡辺さんの慰めとなったのは、自分を主人公に見立てたロマンチックな物語を夢想することと、お絵描きだったそうです。
いじめに悩んでいた渡辺さんが立ち直るきっかけとなったのが、2年生の終わりの学芸会でした。
「犬のお母さん役だったのですが、舞台に立つと、いじめられっ子の自分を忘れることができたのでしょう。『拍手をもらってとてもうれしかった』と母に伝えたそうです。その後、3年生のときの担任の先生が、歌を歌えば『いいね』、作文を書けば『うまいね』とみんなの前で褒めてくれたことで自信がつき、学校生活に溶け込むことができるようになりました。そして5年生のとき、6年生を送る会で、人生で初めて自分で脚本を書いて演出・主演を務めたお芝居が大好評だったんですよ」。
こうして「得意なこと」を見つけた渡辺さんは、中学、高校でどんどん演劇にのめり込んでいきます。
大好きな演劇をやれるから貧乏だってつらくなかった
渡辺さんが「演劇のプロになろう」と決意したのは高校1年生のときです。
進学した県内有数の女子高では演劇部に入部。熱心な部員たちと毎日のように演劇論を戦わせたり、演出から照明、美術もすべて自分たちで手作りして一つの舞台を作り上げていくことに夢中でした。
そんなころ、文学座の山形公演を鑑賞する機会が訪れます。女性の演出が珍しかった時代、長岡輝子さんが主演女優と演出を務めた『ガラスの動物園』の舞台でした。
「当時の私は、演劇に没頭したいという理想と、娘に大学進学をと望む親の期待に沿わなければならないという現実とに板挟みになっていて、劇中のローラというちょっと神経質でデリケートな性格の娘に自分を重ね合わせて観ていました。幕が下りたとき、どんなに人生がうまくいかなくとも、『私は生きていていいのだ。明日からまた生きていける』という感動に震え、涙が止まりませんでした」。
そこで渡辺さんは、長岡輝子さんに会うために楽屋へ。舞台裏では、先ほどまで舞台に立っていた江守徹さんや高橋悦史さんも含めて全員で掃除をしたり、トラックに道具箱を搬入したりしていました。
「主役も裏方も一緒になって作業をする姿を見て、『これが演劇の世界というものなんだ』、『本当にかっこいい!』と思いました。そこで長岡さんに『役者になりたい。ただ、大学を受験するか、すぐに上京して芝居を始めるか迷っている』と相談したところ、長岡さんは『役者に学歴は必要ないから、すぐ東京に来た方がいいわよ』と。そのひと言で心が決まり、次の日からもう、学校の勉強はやめちゃいました」。
「芝居をやるために上京する」という渡辺さんに対し、両親も高校の先生も猛反対します。
「父は地元の国立大に行って自分と同じ教師になってほしい、母は洋裁を学んでブティックでも経営してもらいたいと考えていたようです。2人とも“女でも手に職を”という考えは持っていましたが、『演劇なんかでは絶対に食えない、苦労する』と。でも私の決意は固く、とうとう、『学校に進学するのなら』と両親は東京行きを許してくれました」。
こうして入学したのは、舞台芸術学院(以下、舞芸)という演劇の学校です。風呂がなくトイレも共同のアパートで、独り暮らしを始めました。仕送りは月3万円。アルバイトをしていたものの生活はかつかつで、月初なのに所持金が13円しか残っていないこともあったそうです。
「それでもプロをめざして夢いっぱいの私は、お腹が空いていても、週1回しか銭湯に行けなくても、おしゃれができなくても、まったくつらいと思ったことはありませんでした。成人式は卒業公演の準備に奔走していたときで、同じ劇団の女の子と3人でアパートで乾杯しただけ。それも今は楽しい思い出です」。
舞芸を卒業後、渡辺さんは青俳という劇団の演出部に所属します。同時に舞芸時代の先生と仲間5人で自主公演を行い、さらに舞芸の授業の戯曲や作曲、美術を手伝うなど掛け持ちで、演劇のことなら何にでも挑戦していきます。
「青俳では演出助手、舞台監督助手、美術、衣装、照明、音楽、公演プログラム作り、稽古場の雑用まで何でもこなしながら演出の勉強をしました。女性は私だけで、男の人たちに混じって何日も泊まり込むことが当たり前の生活。1週間寝ずに戯曲を書いたことや、トイレに行くのも忘れるくらい夢中になっていて膀胱炎になったこともあります。このころもお金がなくて、終電の時間を過ぎて、新宿から池袋まで歩いて帰ったこともありましたが、好きなことに熱中できる、それだけで幸せでした」。
今だってお金の苦労と無縁ではない
1978年、23歳の渡辺さんは舞芸仲間たちと4人で最初の劇団「2○○(にじゅうまる)」を旗揚げ(その後劇団「3○○(さんじゅうまる)」に改名)します。そのときも渡辺さんは脚本・演出・美術、作曲まで手がける活躍ぶりでした。
当初は、観客がわずか5人ということもありましたが、熱心なファンの口コミで徐々に作品が認められ、3〇〇の公演は次第に大盛況に。そして大きな転機となったのが、28歳の1983年、『ゲゲゲのげ』で劇作家の登竜門といわれる岸田國士(きしだくにお)戯曲賞を受賞したこと。また、女優としてNHKの『おしん』に出演したことをきっかけに、渡辺さんの名前は全国に知れ渡ります。商業演劇への出演や自分の劇団以外の戯曲や演出、エッセイなどの仕事も増えていき、経済的に余裕ができたことで、ようやく両親に学生時代の借金を返すこともできたといいます。
その後、劇団の解散や、新たな劇団の結成などを経て、現在渡辺さんは、企画集団「オフィス3○○」を主宰し新たな表現の舞台をめざすと同時に、演劇塾を立ち上げて若い役者を育てています。また女優として、テレビや映画などで幅広く活躍していることはご存じの通りです。
売れっ子となった今でも、演劇を続けている限り、お金の苦労と無縁ではありません。3000人も入るような大劇場でのロングラン公演は別として、200人程度の劇場ではたとえ満員になっても採算ギリギリなのが常。プロデュース型(劇団メンバーではなく、公演ごとに役者を集めるスタイル)の公演では、役者にもスタッフにも給料を払わなければならず、予算を立てる時点ですでに赤字ということもあるそうです。
「文化庁などから助成金が入れば赤字を出さずにすみますが、ダメな場合は自腹。先日も給料を払うために金融機関からお金を借りたんです」。

お金に苦労すると分かっていても、小劇場での芝居にこだわるのは、「やりたい演劇をやる」という信念があるから。
「大劇場で大勢の人に楽しんで帰ってもらう演劇ももちろんやりがいがあります。でも、それだけではなく、小劇場で観客と一つの空間の中で、私の世界観をもっとストレートに表現したいんです。例えばピカソの『ゲルニカ』という作品を見て、『戦争の悲惨さを描いている』ということをすぐに理解する人と、『まったく分からない』という人がいるように、たとえ少数にしか理解できないとしても、きちんとメッセージを受け止めてくれる人がいればそれでいい。それこそがアートだと思うんです。私は自分の演劇が一番面白いと思ってやっています。いまだ出会ったことのないような舞台空間をゼロから創り上げるのが、表現者としての醍醐味ですね」。
演劇を通じて人々の心に寄り添いたい
渡辺さんは一貫して、演劇を通じて社会に生きる人びとの怒りや悲しみ、楽しいことやうれしい思いを、ときには過激に、シュールに、そしてユーモアいっぱいに表現してきました。そんな渡辺さんの目に、今の社会はどう映っているのでしょうか。
「日本は戦後の貧しかった時代を一生懸命に乗り越え、やっとここまで豊かになったのに、最近は勉強をしたいけれど高校を中退する人が増えているなんていうことを聞くと、なんだか時代が逆戻りしている感じがしますね。経済的な格差も広がっているというし、貧困が貧困を生む社会構造は変えなければならないと思います」。
とはいえ渡辺さんは、その思いを声高に主張するわけではありません。渡辺さんがめざすのは、まじめに毎日を生きる人びとの心に寄り添い、生きる勇気を感じてもらえる舞台です。
まだ若くお金もなかった23歳のときの旗揚げ公演『モスラ』では、劇団メンバー全員を主役に、「貧乏であっても、夢や愛があれば心ひとつで我が家はポカポカ」と歌い上げました。代表作『ゲゲゲのげ』は、いじめられっ子の主人公と『ゲゲゲの鬼太郎』の鬼太郎が学校に棲む妖怪を退治しようと出かける話を通して、いじめる・いじめられる関係の謎や、世の中の犠牲となってしまう理不尽さ、そんな人を励ますやさしい人びとの姿をユーモアを交えて描いています。
また、東日本大震災後には、火山の噴火によって街ごと消滅した古代イタリアのポンペイと宮城県を、時空を越えて行き来する音楽劇『あかい壁の家』を創作。山形、仙台、久慈をはじめ全国各地で公演し、被災地に思いを寄せました。
「宮沢賢治に『世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない』という言葉があります。私の思いも同じ。別に私が正義感が強いというわけじゃなく、昭和30年代生まれにはそういう価値観を持っている人って多いのでは。子どものころに読んだ本や漫画、受けた教育も影響しているのかもしれません。物語に出てくるのは、いつも決まって貧しい生活の中でも努力と忍耐で成功する主人公でした。それを生まれながらにしてお金持ちで意地悪な人が出てきて邪魔をする。『お金持ちは悪人』で、『お金で人の心を動かすのは醜いこと』だとすりこまれてきたんですね(笑)」。
高校1年生のときに『ガラスの動物園』を観て、生きる勇気をもらえたように、「これからも、観る人を心の底から笑わせて、泣かせて、そして最後は人の幸せを思いやったり、生きることってすてきだなと幸福感に包まれるような芝居を創り続けていきたい」と話す渡辺さんです。
![]()
本インタビューは、金融広報中央委員会発行の広報誌「くらし塾 きんゆう塾」Vol.38 2016年秋号から転載しています。