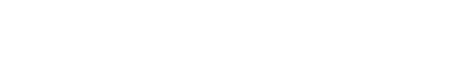おかねのね
いろいろな預金と利子
目的に応じて使い分ける預金の種類
主な預金とその用途を把握しましょう。
- 「普通預金」もっとも広く知られ、なじみ深い預金です。公共料金やクレジットカードの利用代金、住宅ローンの支払いなどの自動引き落とし、給与や年金などの自動受け取りができます。生活に便利なサービスを利用して、お財布代わりに日常的に使えます。
- 「定期預金」半年、1年、3年後など、預け入れるときにその期間を決めて満期日に引き出せます。金利が預金の中では高いという特徴があります。
- 「当座預金」当座預金は主に会社が利用し、手形や小切手の支払いに使われる預金です。利息(利子)はつきません。
- 「貯蓄預金」定められた最低基準額以上の残高があると、普通預金より金利が高くなることが多い預金です。出し入れ自由ですが、普通預金と異なり、公共料金やクレジットカードの自動引き落としはできません。
- 「総合口座」普通預金と定期預金などを組み合わせた預金口座です。「貯める」、「増やす」、「受け取る」、「支払う」、「借りる」といった総合的な機能を有します。
「普通預金」より「定期預金」の方が、金利が高い理由
銀行は預かったお金を、資金を必要とする企業に貸し出して運用しています。「普通預金」のようにお金が自由に引き出される可能性があると落ち着いて計画通りに運用することができません。「定期預金」はお金を預ける期間が決まっているため、銀行はその期間、お金を社会に流通させることができます。安定的に利用できることから金利を少し高目にしているわけです。
金利を意識すること
金利は1年間(365日)の間に生じる利子を%の割合で示したものです。このため、「3か月もの定期預金 0.3%」と表示されている場合、満期を迎えた3か月後の利子は元本の0.075%となります。つまり、10万円を定期預金として預けても、300円の利子が付くわけではなく、その四分の一の75円が利子となります(税金や実際に預ける日数は、ここでは考慮していません)。 また、利子を計算するに当たっては、その金利が単利であるのか複利であるのかに注意する必要があります。
※現在、3か月複利の金融商品はありません。
用語集もご覧下さい。
もっと調べたいときには・・・
このテーマも学んでみよう!
- 銀行に預けたお金ってふえるの?<おかねのやくわり道場>

- 銀行って何をするところ?<おかねのやくわり道場>