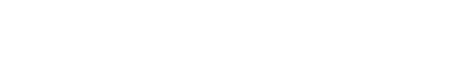おかねのね
お年玉どうしようかな
お年玉の与え方
お年玉の季節になると、金額や管理に頭を悩ませる方が多いと思います。お年玉の考え方は各家庭によりさまざまで、慣習もあるでしょう。楽しみにしているおじいちゃん、おばあちゃんの気持ちもわかります。親戚同士では子どもの有無や数も違うので、事前に打ち合わせて、年齢に合わせた基準を決めておくと悩まないで済みます。「お年玉の使い道は、おうちの人と相談してね」と一言添えて渡すことも大事です。
お年玉をくれた人のことを考える
子どもに助言
友だち同士でお年玉の額が話題に出ることもあるでしょう。しかし、子どもを思う優しい気持ちは、お年玉の有無や金額の多さではないということを親が話すことは、とても大切なことです。また、お年玉が労働の対価のお給料や年金の中から出ていることを、子どもの成長過程に沿って説明していくことも、お金の教育につながります。お礼の気持ちを言葉や手紙で相手に伝えさせましょう。
お年玉でお金の管理のトレーニング
月々のおこづかいの何十倍にもなる大金をどのように管理したらよいのでしょうか。長い人生でお金を上手に管理して使っていくために、お年玉をよい機会としてトレーニングをしていきましょう。
- 欲しいものを紙に書いて、順番を付けて自ら選ばせる。
何かを選び、何かをあきらめる習慣をつけましょう。
※欲しいものに関する考え方については、「ほしいもの?必要なもの?」をご覧ください。
ほしいもの?必要なもの?<おかねのつかい方道場>
- 子どもの夢を聞いて、夢のための貯金を始める。
子どものために支出したのであっても、親が断りなく使ってしまうと、子どもはがっかりするかもしれません。夢のために目的を持って貯めていくことを確認して、一緒に金融機関に預けに行ってはいかがでしょう。進学など、将来の進路に向けて必要な資金を親子で貯めていくのも、夢のための貯金といえます。 - 寄付や募金などの機会があったら、その中から出せるようにする。
自分のお金の中から払うことで、寄付や募金の意義を認識できます。
子どもの喜ぶ顔を見ると自由に使わせたい気持ちになりますが、ガマンも大切です。また、手元に大金を持たせたまま使い道も自由にしてしまうと、貸し借りやおごりおごられなどの問題も出てきます。親に内緒で、友だちとの間で高額なものの売り買いをした例もあります。臨時収入には、貯金をすることで制限を設けましょう。浪費癖がつかないように、わが家のルールを決めて、親子で納得がいくまで、よく話し合いましょう。
お年玉って何?
お年玉の由来は、年神(としがみ)に供えた鏡餅をお下がりとして子どもに分け与えたところから、おとしだま、としだま、となった説や、鏡餅の丸い形からきているなどの説があります。金品を贈るようになったのは室町時代からといわれます。日本のほかには、旧正月にお金を贈る風習が中国・韓国などで見られます。
クリスマスや誕生日のプレゼント、お正月のお年玉を、子どもは楽しみにしています。しかし世界の中には、お年玉をもらうどころか、子どもが働いて家計を支えている国もあることを忘れてはなりません。戦禍や貧困の下、十分な医療や教育が受けられない子どもたちに何かできることはないか、親子で考えてみる機会にしたいものですね。
用語集もご覧下さい。
もっと調べたいときには・・・
- 子どものくらしとお金に関する調査(第3回)2015年度
- お年玉の金額や使い方について聞いています。
このテーマも学んでみよう!
- ほしいもの?必要なもの?<おかねのつかい方道場>

- 銀行に預けたお金ってふえるの?<おかねのやくわり道場>