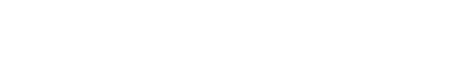おかねのね
ねだんってどうつける?
商店には、さまざまな商品が並んでいて、私たちはその中から購入するものを選んでいます。一方、商店の側では、特売や値引きなどで他の店と差をつけて消費者が買いたくなるように商品を安くしたり、逆に高級感を演出するため他より高い価格を設定したりと、値段の付け方を工夫しています。値段が単に安い・高いではなく、どのような戦略や背景があって、その価格がその商品に付けられているのかを考えながら、購入の有無を判断することを心がけましょう。
例えば、安いものを見つけると、ついしてしまいがちなのが「まとめ買い」。トイレットペーパーなどの日用品や、乾物、缶詰、瓶詰の保存食品などは、安いときにまとめ買いする方も多いのではないでしょうか。生活費の節約になる、得した気分になる、などメリットを感じることができます。商店の側も大量に仕入れてコストを下げることや、他の商品の購入に結びつけることを狙っています。ただし、価格が安くなっているからといってまとめ買いしたら、実は不要なモノも買っていたということもあります。安いとはいっても、日用品ならば節約できるのはせいぜい数十円ぐらい。冷静に計算すればそれほど得ではないですし、保管する場所が必要、消費ペースをかえって早めてしまうなど、まとめ買いにも欠点はあります。まとめ買いをするか、その都度買うか、消費ペースを把握して節約効果が高まるような買い方をしたいものです。
値段のほかに気をつけたいこと
賢い消費者になるためには、モノやサービスの価格のほかにも、入手できる情報をもとに、比較してから選ぶ習慣を身に付けることが大切です。個々の商品の産地や品質が異なっているためです。例えば、スーパーで子どもと買い物をするとき、手に取った品物の商品ラベルを一緒に見ながら、産地、原材料、添加物、消費期限などの表示を確認するという習慣を付けてはどうでしょうか。子どもにラベルの読み方を説明しながら、どうしてその商品を選ぶのかという理由も伝えて買い物することで、子どもに目的にあった品質のものをムダなく選ぶ方法を学ばせることができます。
また、食品を選ぶ際には、JASマークを目印にすることも考えられます。JASマークは、一定の品質や特色をもっている製品に付けられるマークですので、基準にすると便利です。
もっと調べたいときには・・・
- JAS規格について(農林水産省へリンク)