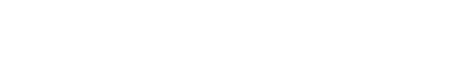おかねのね
“もしも!”をふせぐ、“もしも”にそなえる
非常食や非常持ち出し品の準備、親子でいっしょに
いざというときのために、非常食や非常持ち出し品の準備はできていますか。
地震や台風あるいは大きな事故のニュースなどを見聞きしたことを機に、災害を身近に感じて非常用品を購入したという人は多いと思います。でも、一度準備したから安心・・・というわけにはいきません。食料品やペットボトルの飲料水・電池・カセットコンロなど保管しているうちに期限が切れてしまうものも含まれているからです。ポイントは「一度ではなく、定期的に見直す」です。
【しらべてみよう!】で紹介したリストなどを活用して、「わが家の非常品リスト」について親子で話し合ってみましょう。その後、一緒に買い物に行けば、お金の使い方を考える良い経験になり、また親子で防災意識を高めることにもつながります。
子どもに助言
近頃は、様々な専用のグッズも販売されています。確かに、あれば安心という気持ちでどれも必要なものと思いがちですが、非常用品は必ず使うことになるものばかりではありません。子どもには、家計の予算の中で過不足のないように購入計画を立てる必要があることを伝えましょう。
新しい物を購入しなくても、家にあるものに少し手を加えたり、目的を変えて代用できないかを考えたりしながら準備をしていきましょう。
また、非常食などの使用・消費に期限のあるものについては、無駄なく有効に備蓄・活用する方法として「ローリングストック方式」が参考になります。
日頃の備えが“もしも”の際に差を生む
事故や災害が発生してしまうと、家族の生活には経済的にも精神的にも大きなマイナスの影響が生じます。ですから、誰しも自分の身に降りかかるなんて考えたくはないものです。
でも、起きてほしくないことだから考えないのではなく、まず事故や災害を防ぐためにできることを考えましょう。そして、もしも実際に起きてしまった場合にでも、被害や影響を最小限にとどめるために、家族みんなでできることが何かを事前に考え、取り組んでおくことが大切なことなのです。
ローリングストック法
数年間も保存できる特別な非常食にこだわらず、1年程度保存できるものを対象とする代わりに、定期的(1ヶ月に1回など)に食べて、食べた分を買い足す・・・を繰り返すことで常に新しい非常食を備蓄する方法です。日頃食べ慣れたインスタント食品やレトルト食品・缶詰が対象となるため、「食べながら備える」ことが可能となります。災害時には、食べ慣れたものを食べることができるというメリットもあります。
もっと調べたいときには・・・
- できることから始めよう!防災対策第3回(内閣府 広報ぼうさい<平成25年度冬号>) (内閣府へリンク)
- 災害時に命を守る一人一人の防災対策(政府広報オンライン)