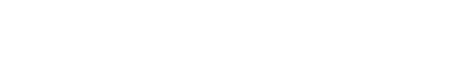おかねのね
みんなはおうちの何がかり?
子どもたちが、初めて所属する社会は家庭です。家庭は、かけがえのない自分の居場所です。生活の場であり、団らんの場であり、また集団や社会の助け合う仕組みを学ぶ場ともなるのです。そのような点からも、子どもたちの人格形成の基礎はその家庭にあると言ってよいのです。毎日ともに過ごしている家族が楽しく幸せに暮らせるために、子どもたちにできることを一緒に考えて、役割を任せてみましょう。やると決めたことに責任を持たせることも大切です。最初は自分の身の回りのことから始め、そこから少しずつ、料理や掃除など普段みなさんがしていることの一部分を任せるようにしていくと良いでしょう。仕事が決まったら当番表をつくって目につくところに張り出し、自分の役割を意識させることも一つの方法です。
子どもに助言
子どもには自分の身の回りのことや家の「係活動」を通して、家族の一員としての意識や自覚が芽生えるように促しましょう。自分が部屋を散らかしたりすることによって、家族に片付けなどの手間をかけさせ、家の居心地を悪くしてしまうということがわかるとよいですね。まずは自分のことは自分でするということが結果的には家族の負担を減らし、助けていることにつながると自覚することから、自発的な手伝いができるようになるでしょう。そして、大切な家族の一員であることや助け合うことの意味について手伝いなどを通じて繰り返し伝えていきましょう。
子どもたちが行っていることがどれだけ役に立っているかを伝えるために、感謝の言葉や、やったことを知っている、または認めているという旨の言葉を意識的にかけていきましょう。そうすることで、人のためにしているということがわかり、自分の仕事の意義が実感できることと思います。
「自分のことを自分でする」、「家の中での役割を自覚して進んで働く」ということは、将来、人に頼ってばかりではなく、自分にできることは何かと考え、自立する姿勢を身に付けることにもつながります。
つまり、家庭生活の中で、家族が互いの立場を尊重しながら家族に貢献することの大切さに気づいていくようになると、子ども自身も家族の中での自分の立場や役割を自覚できるようになってきます。このことで、自分も兄弟姉妹などとともにその家族の一員として積極的に役に立とうとする精神が芽生えるのです。自分なりにできる手伝いという行為を通して、家庭生活に貢献すれば、家族のために役に立つ喜びが実感できるようになります。