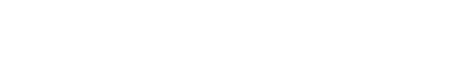おかねのね
おてつだい、がんばるぞ!
家の手伝いを通して、家族はみんなで助け合って生活していること、自分もその家族の一員だということを認識させることは大切なことです。また、それに加えて手伝いができたときは積極的にほめて子どもに自信をもたせてあげましょう。子どもにできる手伝いは限られているかもしれませんが、年齢に応じてできることから始めさせたいものです。
子どもに助言
どんな仕事があるのか、子どもには何ができるかを親子で紙に書き出して、その中から子どもができる仕事に気づかせ、親がやってほしいと考えているもの、子どもができると思うもの、あるいはやりたいものを話し合ってみるのもよいでしょう。最初から上手にはできません。親はまず一緒にやって教えてあげましょう。多少の失敗があってもあたたかく見守ることが大切です。
また、お手伝いに対しておこづかいを与えるかどうかについてはさまざまな考え方があるでしょう。家の手伝いは家族の一員として当たり前のことであり、報酬を与えるのは好ましくないという考えがある一方で、お手伝いのほうびとしておこづかいを渡すという考え方もあり、一概にどちらが良いとはいえません。日常のこととは違った特別なお手伝いをした場合におこづかいを与えるというやり方は、労働とお金の関係を考えさせる機会になるとも考えられます。
毎月のおこづかい額の決め方については、「定額」、「定額+報酬(歩合)」など家庭によっていろいろ工夫されていることでしょう。お手伝いをポイント制などにしておこづかい額に反映させている家庭もあるようです。また一例として、基本額を決めておき、決められた手伝いができなかった場合には減額するという方法もあります。このようにおこづかい額に手伝いの実績状況を反映させる場合には、決められたことがきちんとできたかを親子で確認してから渡すようにしましょう。そうすることで、責任ある仕事をして初めてお金がもらえることが子どもにも認識でき、労働とお金(対価)の関係についての理解も深まるでしょう。
子どももいずれ成長して家事をしなくてはいけない時期が来ます。安易に報酬を与えすぎて、大人になってから「報酬がないからやらない」、「報酬があるならやってもいい」とならないよう、親子で約束ごとをしっかり決め、時として厳しく見守ることがポイントです。
どういうときにおこづかいをもらうかという問いに対しては、約半数の子どもが「おてつだいをしたとき」と回答しています。
| 小学校低学年 | 小学校中学年 | 小学校高学年 | |
|---|---|---|---|
| なにか、買いたいものがあるとき | 21.4 | 21.1 | 32.0 |
| お手伝いをしたとき | 51.0 | 47.9 | 40.7 |
| テストの点数が良かったとき | 18.2 | 19.9 | 17.9 |
| おじいさんやおばあさんに会ったとき | 19.8 | 23.9 | 35.3 |
| お祭りがあるとき | 31.0 | 41.8 | 52.8 |
| おじさんや、おばさん、いとこに会ったとき | 11.2 | 13.0 | 19.3 |
| 友だちと遊びに行くとき | 10.1 | 16.5 | 32.9 |
| 家の買い物をしておつりをもらったとき | 21.8 | 21.6 | 25.9 |
資料:子どものくらしとお金に関する調査(第3回)2015年度
*学年ごとに回答数を総数で割って出した数字(%)。
このテーマも学んでみよう!
- みんなはおうちの何がかり?<おかねとしごと道場>

- お手伝いは最後まで<おかねとしごと道場>