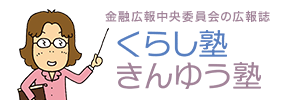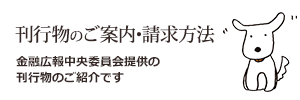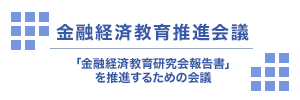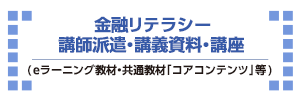江戸時代に学ぶ お金と暮らし
第3回 情報を制する者が相場を制する!江戸時代のトレーダーたち

初心者・一般向け
タグ(キーワード)
- 金融リテラシー
- 投資
前回、江戸時代中期以降の江戸幕府や大名が、資産運用(当時の言葉では「利殖(貨殖)」)を盛んに行うようになっていたことを紹介しました。
お金に疎(うと)いと思われがちな武士たちですら資産運用に熱心だったのですから、商人たちは言うまでもありません。
そして一部の庶民も投資に積極的でした。そこで、今回と次回(最終回)では、江戸時代の庶民による投資活動について、その実態に迫っていきます。
経済新聞社のさきがけ?―状屋の活動―
現代では、株式投資や債券投資など、日ごろから投資活動に携わっている人々にとって、スマートフォンは必須のアイテムです。
時々刻々と変化する相場の状況を把握し、何か大きな出来事が起きたときに、ただちに対応できるようにしておくためにも、小まめな情報収集は欠かせません。
もちろん、ドンと構える、というタイプの投資家もおられるでしょうから、一概にはいえませんが、少なくとも投資活動と情報収集は切っても切り離せない関係にある、ということは間違いありません。
江戸時代のトレーダーたちも、情報収集に余念がありませんでした。
堂島米市場に注文を出す人々が各地に登場し、江戸時代の後期には、堂島で活躍した米仲買(現代の証券会社に近い存在)が出す注文のうち、8割から9割はこうした顧客からの注文で占められるまでになっていきました。
現代の株式市場では、市場で売買を行う権利を保有する証券会社が顧客からの注文を取り次ぎ、手数料を受け取っていますが、堂島の米仲買も、顧客からの注文を取り次ぐことで、手数料収入を得ていたのです。
米仲買が取り次いだ注文の多くが、「帳合米(ちょうあいまい)商い」、現代でいうところのデリバティブ(金融派生商品)取引でした。
前回紹介した米切手の取引は、いわゆるプロフェッショナル間の取引であったのに対して、帳合米商いは、広く庶民にも開かれていました。
この帳合米商いについて、ここでは深掘りしませんが、興味のある方は、拙著『大坂堂島米市場』(講談社、2018年)などを参照してください。
全国各地の投資家に対して、堂島米市場の様子を伝えたのが「状屋(じょうや)」と呼ばれた人々でした。
史料によれば、およそ米相場に関わる情報を集め、それを書面にしたためて売ることを生業(なりわい)にしたのが状屋だそうで、経済新聞社のさきがけともいえる存在でした。
状屋が作成した書状(「相場状」、「相場書(がき)」などと呼ばれました)には、堂島米市場で形成された日々の米価はもとより、時には全国各地の作柄などの情報も記載されました。
そして、こうした書状を各地に運ぶことに特化した集団が、「米飛脚(こめびきゃく)」でした。
速報サービスを担った米飛脚
当時の庶民が利用した町飛脚は、書状の伝送をはじめ、荷物や現金の輸送も担うことがありましたが、米飛脚は相場書の伝送に専門化し、伝送速度の速さを売りとしました。
もっとも、これは彼らの走る速度が速かったというとではなく、伝送間隔が短かったことによります。
現存する米飛脚の引き札(現代でいうチラシ)から、彼らのサービス内容を確認してみましょう(図表)。
この引き札の作成年代は不詳ですが、刷り物であることから、相当数が作成・配布され、米飛脚間の競争があったことをうかがわせます。
この引き札の差出人である堺屋記次郎(さかいやきじろう)と、その出店の堺屋佐兵衛(さかいやさへえ)が店を構えた渡辺橋は、堂島米市場のすぐ西側に位置しており(現在も橋の名が残っています)、米飛脚が店を構える場としては都合がよかったと思われます。
ここで着目すべきは、「毎日出シ」の文言です。
兵庫灘、播州路、泉州路、池田、伊丹、三田、江州路、伊賀、伊勢については、毎日米飛脚を出すことをうたっています。

- (出所)
- 公益財団法人三井文庫蔵
江戸時代に庶民が利用した町飛脚は、書状や荷物を受け取り次第、ただちに出立するわけではありませんでした(希望するタイミングで書状を発送する場合には、追加料金を支払う必要がありました)。
これに対して米飛脚は、毎日出立していました。さらに、追加料金を支払う顧客のために、1日に複数回出立することもありました。
さらに、図表の米飛脚引き札から兵庫灘への出立時刻に着目すると、並便が出発するのは九ツ半時(午後1時前後)、早便が出発するのは五ツ時(午前8時前後)、四ツ半時(午前11時前後)、八ツ時(午後2時前後)となっていることが分かります。
実はこれらの時刻は、堂島米市場での取引の節目と正確に対応しています。
「並便」の出立時刻は、堂島米市場における米切手取引の終了時刻、「早便」が出立した3回は、それぞれ帳合米商いの開始時刻、米切手取引の開始時刻、帳合米商いの終了時刻に対応していました。
つまり、「並便」は米切手取引の終値が確定した段階で発送され、「早便」は帳合米商いの始値、米切手取引の始値、帳合米商いの終値が確定され次第、発送されていたのです。
時々刻々と変化する米相場に関心を寄せる人々に、毎日、それも相場の節目で確実かつ定期的に出立して相場書を届けたのが米飛脚だったのです。
江戸時代の通信革命―旗振り通信の登場―
伝送速度を売りにした米飛脚でしたが、それでもなお飽き足らない人々がいました。
江戸時代において、そのニーズに応えたのが「旗振り通信」でした。
遅くとも18世紀初頭には、旗や幟(のぼり)などを利用した通信が広く行われていたと推定されています(柴田昭彦『旗振り山』ナカニシヤ出版、2006年)。
残念ながら、江戸時代における具体的な通信技術に関する記録は残されていないのですが、明治以降のそれから推測することは可能です。
明治42(1909)年に、大阪市役所が行った調査(「旗振信号の沿革及仕方附、伝書鳩の事」)によれば、情報の送り手が旗振り通信に用いた旗には、大旗(約910×1,666㎜)と小旗(約606×1,060㎜)とがありました。

- (出所)
- 大阪府立中之島図書館蔵
天気がよい時は小旗、曇天の時は大旗を、また山上にある中継点では黒旗を、低地にある中継点では白旗を用いた、とされています。
そして、その旗振信号の情報を、情報の受け手は望遠鏡を使って受け取っていました。
旗振り通信研究の第一人者、柴田昭彦氏が、明治期に利用された旗振り場の間隔を実測したところによれば、その距離は短いもので1里(約4㎞)から、長いもので5里半(約22㎞)、平均すれば3里(約12㎞)。
伝承されている大阪・地方都市間の通信所用時間と、旗振り場の平均的な間隔からすれば、通信速度は平均時速720㎞となるそうです(前掲、柴田氏著書)。
これは小型のプロペラ機とほぼ同じぐらいの速度なのです。
旗振り通信頻度については地域差があったようですが、1日に5〜10回が平均的だったそうです。
明治以降の、大阪からの通信時間は、和歌山が3分、京都が4分、神戸が7分、桑名が10分、岡山が15分、広島が40分弱であったとされます。
望遠鏡の倍率に限界があった江戸時代にあっては、より長い時間を要したものと推定されますが、それでも飛脚よりも速かったことは想像に難くありません。

(著者蔵)
江戸幕府は、この旗振り通信による相場報知を禁止していたため、表立って記録に残されることは少なく、江戸時代における実態はよく分かっていません。
しかし、大坂―京都間、大坂―大津間では間違いなく行われていたことが史料によって裏付けられています。
このうち、大坂堂島米市場に次ぐ規模を誇った「御用米会所(ごようこめかいしょ)」を擁した大津では、大坂から毎日、飛脚と旗振り通信によって相場情報を取り寄せて、売買が行われていました。
ちょうど、日本の株式市場参加者がニューヨークの株式市場の情報を見ながら取引を行っているようなものです。
旗振り通信が導入されるまでは、大津の米相場は大坂の米相場から1日遅れで追随していたのに対し、旗振り通信が導入されて以降は、1日の遅れもなく連動していたことが筆者の研究で明らかになりました。
飛脚から旗振り通信へと情報伝達の速度が上昇したことに伴って、2つの市場の価格が連動する速度も高まっていたのです。
商人、農民を問わず、堂島米市場での取引は多くの人々の注目を集め、それに伴って情報収集・伝達のスピードも、飛躍的に上昇していきました。
実際、大津の郊外に居住していた農家が、旗振り通信を利用して情報収集を行い、投資活動に活かしていたことも分かっています。
毎日、それも決まった時刻に飛脚が出立することが求められたほど、そして旗振り通信が利用されるほど、江戸時代の相場情報伝達に求められる速報性は高まっていました。
この変化をもたらしたのが、江戸時代に暮らした庶民の投資熱だったのです。
- 江戸時代の大坂は「大坂」、近代以降は「大阪」と表記しています。
![]()
本コンテンツは、金融広報中央委員会発行の広報誌「くらし塾 きんゆう塾」Vol.59 2022年冬号(2022年(令和4年)1月発刊)から転載しています。
広報誌「くらし塾 きんゆう塾」目次