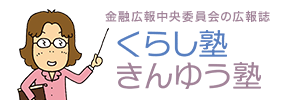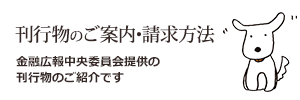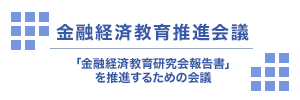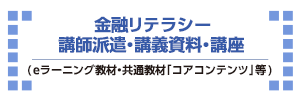著名人・有識者が語る ~インタビュー~
音楽は生きる力
ピアニスト 梯 剛之
生後間もなく病気で視力を失いながらも、天賦の才能と、たゆまぬ努力、そして、それを支える母親の深い愛情によって今日では世界的なピアニストとして 活躍されている梯剛之さん。
現在は「子どもに伝えるクラシック」プロジェクトを展開している梯さんに、音楽への想いや、母と子で培った生きる力について、金融広報中央委員会の恵谷事務局長がお話を伺いました。

梯さんの母・侑子さん(左)と、今回インタビュアーを務めた恵谷英雄事務局長(右)
梯 剛之
(かけはし・たけし)
1977年東京都生まれ。父はビオラ奏者、母は声楽家。小児ガンにより生後1カ月で失明するが、音に対する非凡な才能を見せ、4歳半より本格的にピアノを始める。90年小学校卒業と同時に渡欧し、ウィーン国立音楽大学準備科に入学。同年再び目に悪性腫瘍を患い帰国し手術。翌年ウィーンでの勉強を再開した。98年ロン=ティボー国際音楽コンクール第2位で注目を集め、以後、世界的なピアニストとして活躍を続けている。
音楽との出会い

「生後間もないころから音楽はいつも身近な存在でした」。朗らかな笑顔で、音楽との出会いをそう語り始めた梯さん。小児ガンにより生後1カ月で失明。手術後も治療や検査のたびに頭や体を押さえつけられ、まぶたを金具製の医療器具で開けられる日々。そのストレスのためか夜泣きも激しかったそうだが、クラシック音楽のレコードをかけるとぴたりと泣きやんだと言う。
「当時から難しい曲でも静かに聞き入っていたそうです。10カ月を過ぎたころには、お気に入りの一つだったリヒャルト・シュトラウスの『四つの最後の歌』の一節を、レコードに合わせ、非常に正確な音程で歌っていたみたいですよ」
そんな赤ちゃんにとっては、ピアノもおもちゃ代わり。積み木など普通のおもちゃには一切興味を示さないのに、お母さんに抱かれてピアノの前に座ると、手の平で鍵盤を叩いて何十分でも「熱演」を楽しんでいたのだとか。1歳になり、2歳になっても、飽きることなくピアノに向かう姿を見て、ご両親も「これだけ好きなのだからやらせてみよう」と決意。4歳半で本格的にピアノのレッスンを開始し、その才能を高めていくことになる。
ところで、楽譜を見ることができない梯さんは、レッスンの際にもあらかじめ暗譜をして臨んだそうだが、大変な作業ではなかったのだろうか?
「僕は小さいころから演奏を4回ぐらい聞けば、楽譜をほとんど覚えることができました。でも、倍音*の関係で音の響きが多かったり、録音環境によって弾いていない音が聞こえてきたりすることがあります。また、同じ曲なのに演奏家によって速さやアクセントが全然違ったり、音を一つ多く、あるいは少なく弾いているような気がすることもあります。そこで楽譜を正確に覚えるため、今もCDで演奏を聞いた後、母に楽譜を一つ一つ説明してもらっています。速さや表情、休符、アクセント、強弱など、楽譜上の細かな指示を何度も読み返してもらいながら、少しずつ確実に記憶していくのです」
こうして1度覚えてしまえば何年たっても忘れない記憶力と、驚異的な耳のよさ。「天賦の才」とは、まさにこういうことを言うのだろう。
*倍音 「基音(基の音)」の振動数に対して整数倍の振動数を持つ上の音のこと。例えばピアノで「ド」のキーを叩くと、その1オクターブ上の「ド」や「ソ」、2オクターブ上の「ド」や「ミ」などの「倍音」もかすかに鳴っており、これらは豊かな音色をもらたす効果も生む。
母の愛情に支えられて
梯さんは、自身の子ども時代を「とにかく、大人から教えられることが嫌いで、反発する子だった」と言って笑う。一方で、同年代の子どもが働きかけると、たとえそれまで嫌がっていた事柄でも、好奇心を持って取り組むところがあったそうだ。そうした性質に気付いていたお母さんは、健常児の通う保育園を選び、小学校入学時には署名運動まで起こして梯さんを地元校の普通学級へ入学させた。
「母は常に僕のことを思い、何か困難があれば、それをどう工夫し、どう乗り切ればいいかを一緒に考えてくれました。『とにかくやってみて、ダメだったら、そのときにまた次のことを考えればいい』というのが母の口癖で。何もやらないうちにあきらめることを嫌う人なのです」
困難があれば、工夫し、乗り切る――。この言葉をよく示すエピソードに教科書作りがある。梯さんの入学は許可されたが、盲児用の教科書は準備してはもらえなかった。そこでお母さんは、まだ点字を十分に読めなかった梯さん用に、手で触って分かる教科書を手作りすることになる。さすがに1人では無理でボランティアグループにも手伝ってもらったそうだが、全教科分を6年間。膨大で根気のいる大変な作業だ。そこで、お母さんに、なぜそれほど頑張れたのか伺ってみた。
「やっぱり、子ども以上の宝物はないと思うのです。今までで一番つらかったのは、剛之の命が危険にさらされたとき。自分の産んだちっちゃな赤ちゃんが、もうほとんど見えなくなると言われたこともショックでしたが、でも何としても命だけは守りたかった。そのときの必死な気持ちに比べれば…。命さえあれば、後の苦労はそれ程大変ではありません」
チャレンジから得た力
こうした深い愛情に支えられ、梯さんもさまざまなものを吸収していく。特に、地元の子どもたちとともに学び、遊んだ経験は、今も梯さんの中で大きな財産になっているそうだ。
「音楽漬けにならず、友達と校庭や田んぼなどで遊んだことは、忘れがたい、よい思い出です。体育の授業も結構好きで、鉄棒やマット運動、ドッジボールもやりました。僕の中には、友達がしていることは何でもやってみたいという気持ちがあって、いつも何かに挑戦していたように思います。見える人と競争や比較をするのではなく、ただ自分が納得できるように。そうして一つずつ克服していった経験があるからこそ、何か不安なことがあるときも『何とかな るさ』と思えるようになった。今、僕が舞台に立ち、大勢の人の前で演奏できているのも、こうした経験から培ったところが大きいのではないかと思っています」

「ウィーンに在住して18年。モーツアルトやシューベルトが散歩していた道を歩き、そこに注ぐ光や風、鳥のさえずりに触れたり、彼らの書いた手紙を読むと、この偉大な作曲家たちがとても身近に感じられます。昔の人ではなく、さっきまで僕と話していた人のように、近くに迫ってくるのです」と梯さん(写真は、2008年10月に愛知県知立市で行われた演奏会でのもの)
1998年のロン=ティボー国際音楽コンクールで2位を獲得したのも、こうしたバイタリティがあってこそ。課題曲の中には難解な新曲もあったが、お母さんと2人で何とか準備するしかなかった。
「あの『トゥミュルト』という新曲は、まだCDも何も出ていなかったので大変でした。このタイトルには『都会の喧噪』という意味もあるし、『波の音のざわめき』という意味もある。僕は『波の音』と解釈して演奏したのですが、作曲者はやはり『都会の喧噪』をイメージしていたみたいで、作曲家の名前の付いた賞はいただけませんでした。その方以外の審査員は満場一致で『あなたが一番素敵だった』と言ってくれたのですけど」
その言葉通り、梯さんの演奏への評価は高く、リサイタル賞も受賞。世界4大コンクールの一つに数えられるロン=ティボーにおいて、視覚障害がある人では初の上位入賞を果たした。
音楽の素晴らしさを子どもたちに
これまで演奏活動の傍ら、小児ガン研究や障害者のためのチャリティーコンサートにも積極的に取り組んできた梯さんだが、2006年からはさらに、自身の言葉と演奏で作られたDVDを全国の小学校や特別支援学校、2万4000校に無償配布するプロジェクト「子どもに伝えるクラシック」も展開。全3作のうち、現在までにモーツアルト編とシューベルト編の2作を製作・配布している。
「音楽は僕に生きる力を与えてくれました。ですから、子どもたちにもその素晴らしさを伝え、もっと音楽を好きになってもらい、感動や喜びを共有したいと思ったのです。モーツアルトもシューベルトも、最終作で取り上げるベートーヴェンも、ウィーンで暮らす僕にとって、とても身近に感じられる作曲家。街を歩いているとさまざまな所で彼らの息吹を感じることができます。DVDの中では、彼らが生活した家や散歩した道なども紹介しているので、いろいろ想像しながら楽しんでもらえたらよいですね」
実は、当初は子ども用だからもっとやさしい内容にした方がよかったのではないかと心配していたのだが、それは杞憂だったと言う。
「DVDを見た子どもたちから、いろいろな感想のお手紙をもらいうれしかったです。僕らは全国すべての小学校に送付しているので『うちの学校ではまだ観ていない』という先生や生徒さんがいらしたら、職員室の棚などにないか覗いてみてください(笑)」
最後に、梯さんに今後の夢を伺った。
「ありきたりかもしれませんが、ピアニストとして、よい音を出して、たくさんの方にクラシック音楽を好きになっていただきたいです。それと、僕は演奏会でさまざまな国へ行きますが、残念なことに肌の色の違いに偏見を持つ人がまだ少なくありません。アジア人でありハンディを持つ僕の演奏を通して、知らず知らずのうちについうかうかと(笑)、そうした垣根が取れてしまうような、誰の心も打つ演奏ができたら…。それが僕の夢です」
![]()
本インタビューは、金融広報中央委員会発行の広報誌「くらし塾 きんゆう塾」Vol.7 2009年冬号から転載しています。