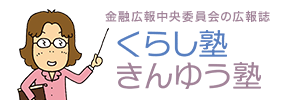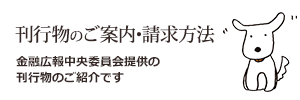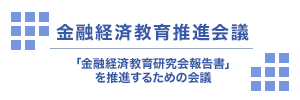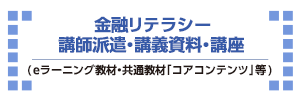著名人・有識者が語る ~インタビュー~
好きになれないはずがない
編集者・評論家 山田 五郎
編集者・評論家である山田五郎さんは、テレビやラジオなどでパーソナリティやコメンテーターも務めるなどさまざまな方面で活躍されています。
出版社に就職後、若者情報誌の編集部に配属され、興味のなかったファッション記事を担当したものの、 そこから「好きになれないはずがない」を信じ、 前向きな好奇心を発揮して、知識や世界を広げてきた山田五郎さんに、仕事についての考え方や人生観、豊かさやお金に対する見方についてうかがいました。

山田 五郎
(やまだ・ごろう)
1958年、東京都生まれ。上智大学文学部在学中にオーストリア・ザルツブルク大学に1年間遊学し西洋美術史を学ぶ。 卒業後、(株)講談社に入社『Hot-Dog PRESS』編集長、総合編纂局担当部長等を経てフリーに。 現在は時計、西洋美術、街づくり、など幅広い分野で講演、執筆活動を続けている。
著書に『百万人のお尻学』(講談社+α文庫)『知識ゼロからの西洋絵画入門』(幻冬舎) 『知識ゼロからの西洋絵画史入門』(幻冬舎)『銀座のすし』(文藝春秋)など TV:『出没!アド街ック天国』(テレビ東京)『ぶらぶら美術博物館』(BS日テレ)他レギュラー出演中。 ラジオ:『デイ・キャッチ』(TBSラジオ)他レギュラー出演中。
ごく普通の家庭で「がまん」を躾られた少年時代

ファッションからホビー、カルチャーまで、その幅広い知見を軽妙な語り口で披露し、人々を魅了する山田さん。 いったいどんな少年時代を過ごしたのだろうと訊ねると、「とくに豊かでも貧しくもない典型的なサラリーマン家庭。 “何の不幸もないことが逆に不幸”だと悩んだくらい、ごく普通に恵まれた環境でしたね」と独特の表現で自身を振り返ります。
小学5年生のころ、東京から大阪へ引っ越し、高校まで育った山田さんは、 お金についての教訓といえば、「大阪商人気質」の祖父の言葉を思い出すと言います。
「将棋をすると、子ども相手に平気でズルをする。後で気づいて指摘しても、 『そんなん騙される方が悪い、気づいたら、その場で言わなあかん』なんてシレッとしている。 また、当時、大阪の進学校の多くは公立で、東京は私立が台頭していた時代だったんですが、 『東京では、人より勉強ができるやつが余計に金払わなあかんとは、おかしな話や』なんて言っていましたね。 当時はひどいことを言う人だなあと思っていましたが、見方によっては正論ですよね」と懐かしそうに笑います。
山田さんは三人兄妹の長男で、小学校低学年のころのおこづかいは週30円。
「好きな少年マンガは、こづかいとは別に月刊誌を一誌、買ってもらっていました。 週刊誌は近所に住む従兄弟と分担して買って回し読み。 本なら買ってもらえましたが、『怪獣図鑑』が欲しいと父に頼んでも『恐竜図鑑』を買われてしまう。 そっちの方が勉強になりますからね。戦闘機のプラモデルや「サンダーバード基地」なんかも欲しかったんですけれど、 『お兄ちゃんだからガマンしなさい』が当たり前で、高価なものはなかなか買ってもらえませんでした」。
高度経済成長期に生まれ育った山田さんの少年期は、「欲しいものをガマンする」ことは珍しくなかった時代。 ところが、自身の子どもも含めて今の若い世代の人たちは、何不自由ない時代に育ったためか、 「どうしても欲しい」というものがないようだと山田さんは感じています。
「モノでも情報でも、欲しくなるのは『お金があるから』ではなく、『飢えているから』だと思います。 バブル期は、実は今ほどモノも情報もあふれてはいませんでした。 多くの日本人が知らなかったモノやコトがまだまだたくさん残っていて、 簡単には手に入らないけど努力すれば手が届く。だから憧れ、欲しくなった。 バブル期は、そんな適度な刺激と飢餓感を共有できた最後の時代だったと思います。 今のように、モノも情報もあふれっぱなしの状態では、何を見ても刺激が得られず、 欲しいと思う気持ちがわいてこなくなるのも当然ですよ」。
「だから、せめて教育の場では、モノと情報を与えすぎず、飢餓感を高めることで 、努力して手に入れようとする欲求と、それを実現する力を養うべきではないかと思うんですよ。 便利なIT機器の使い方を教えるなんて、体育の授業でクルマの運転を教えるのと同じこと。 どちらも社会に出てから必要に応じて学んでも間に合います。 学校では、あえて不便な環境を作り、自分の足で走る体力と自分の頭で考える知力を育ててほしいですね」と、 山田さんは自身の子育て経験をふまえ、恵まれ過ぎている時代に疑問を投げかけています。
ダメ社員から、一世を風靡した雑誌の編集長へ
山田さんは大学を卒業後、大手出版社に就職をします。出版・マスコミ業界を選んだ理由は、 「働く時間が不規則だと聞いたから」。
というのも、実は山田さんは学生時代から、「朝起きられない」という理由で、 勤務時間が決まっているアルバイトには馴染めませんでした。結局、自宅でできる通信教育の添削や翻訳の下訳など、 自分で時間をコントロールできるタイプのアルバイトしか続けられなかったそうです。
「でも、新入社員の研修期間中は当然、時間通りに出社しなければならないので、 すぐにダメ社員のレッテルを貼られました。入社当初から遅刻続きで、 人事課長に『もう来なくていい』とか『配属できる部署がない』とか叱られてばかり。 なんとか配属していただけましたが、創刊3年目でまだ軌道に乗っていなかった若者情報誌で、中でも苦戦していたファッション記事の担当に。 編集部も本社屋から離れたプレハブ造りの別館にあり、島流しにあったような気分でした」。
「ダメ社員ですからね、仕方がない」と笑いますが、この編集部で山田さんの才能が一気に開花します。 情報誌の編集の仕事はまさに激務。「朝起きられない」どころか、「家に帰れない」ため、 遅刻のしようもないという環境では、山田さんの最大の欠点は全く問題になりません。 元来、真面目で一生懸命な性格で、雑誌編集に打ち込むことはまったく難しくなかったそうです。
80年代、ちょうどファッション業界にDCブーム(デザイナーズ&キャラクターブランドの洋服の大流行)が到来し、 「男性ファッション誌は売れても30万部が限界」と言われた時代から、一気に60~70万部も売り上げる人気雑誌へと成長します。 山田さんは、ダメ社員から敏腕編集者として大活躍する時代を突っ走っていきました。
山田さんの飛躍には、一見興味のないことや、自分の考えと少々違うことでもまずは受け入れ、 すべての出会いから、あらゆる影響を受けてきたという柔軟な姿勢があります。 思い出の一つとして、新入社員のころ、書店実習先での社長の言葉を紹介してくれました。
「当時は新しい雑誌がどんどん生まれていました。たまたま書店の社長に『お前の会社はなんでこの雑誌を出したのか?』と質問されたので、 『広告収入が見込めるからです』って答えたんですよ。 そうしたら、『バカもん!お前は儲けだけを考えて雑誌を作るのか?自分がどうしても“これが作りたい”という思いはないのか?』と一喝されたんです。 そのときは『この社長、古いな~』としか思えませんでしたが、今はその言葉の意味がよく分かります。 『どうしてもこれを作りたい』『絶対にこれが面白い』という信念もなく、マーケティングや計算だけで作った雑誌は、たとえ一時的に売れても長くは続かない。逆に作り手の抑えきれない情熱がこもった雑誌は、たとえ部数が伸びなくてもそう簡単にはなくなりませんし、仮になくなっても人々の記憶に残る。今でも忘れられない一言ですね」。
好きになるには、「好きになれないはずがない」と信じること
ここまでの話を聞くと、多くの人は、山田さんは好きなことを仕事にできた幸運な人だと思うかもしれません。 ところが驚くことに、「ファッションには興味がなかった」という意外な答えが返ってきました。

ファッション、車、音楽など世の中にはさまざまなジャンルがありますが、 マスコミ・出版業界の人間は、常に時代のトレンドを捉え、あらゆるジャンルのファンを満足させる必要があり、 さらに言えば、時代の最先端を作っていくような魅力ある雑誌づくりが使命です。
「作り手がそのテーマを本当に好きでないと、読者を説得できません。 だから、『興味はないけど仕事だから頑張る』だけでは不十分。 『興味がなくても頑張って好きになる』。つまり、好きになること自体が仕事なんです」。
まさに今の山田さんの原点は、この独自の仕事観にあるのでしょう。 とはいえ、もともと興味のないものを、どうやったら好きになることができるのでしょうか。
「どんなテーマでも、それが好きな読者がたくさんいるからこそ、雑誌で扱うわけですよね。 だとすれば、自分も好きになれないはずがない。多くの人が好きなものには、何らかの魅力が必ずある。 前向きな気持ちで喰らいつけば、何かしら興味が持てる点、好きになれるところが見つかるはずです。 そこを突破口に興味の幅を広げていけば、『好きになれないはずがない』。 そう信じて頑張りました。お陰で、もともとは興味のなかった分野のことにも詳しくなることができたんですよ」。
「たとえばファッションの場合、私が最初に面白いと思えたのは歴史でした。 当時はポストモダン思想がブームで、ファッションを文化史的側面からとらえた名著が相次いで刊行されていたんですよ。 歴史を知ることで、逆に最新の流行にも興味が持てるようになりました。 また、分野を問わず素材や技術には元々、関心があったので、そんなところからデザイナーさんやお店の方との会話が広がり、いろいろ教えていただけました」。
自分のキャリアに対し、「自分のやりたい仕事じゃなかった」と簡単に仕事を辞めてしまったり、 「自己実現」「自分探し」といった点ばかりを重視したりする風潮を山田さんは「やってみて分かることもあるのに、もったいない」と言います。 目の前に与えられた仕事と本気で向き合う大切さを、私たちも山田さんの経験から学ぶことができそうです。
文化・芸術に「お金を有効活用」
山田さんは大学で美術史を専攻し、オーストリアのザルツブルクでの留学経験もあります。 山田さん自身が「本当に好きなこと」はそこが原点。 時計をはじめ、さまざまな美術工芸品に造詣が深く、西洋絵画の見方に関する入門書も上梓されています。
「美術史をやっていたときも、フレスコと油絵の違いといった技術的な話が好きでした。 だからファッションでも素材や縫製に目が行った。デザイナーさんにうかがうと、 『この素材と出会ったからこそ、このデザインが生まれた』なんて話がよくあります。 芸術もファッションも、発想だけでモノは作れません。素材や技術って、実は結構、大切な要素なんですよ」。
物事が成り立つ背景を調べるうち、次々に興味がわいてしまう山田さんが今、執筆準備を進めているのが、 時計が世界の文化史に深いかかわりがあったことを著す、これまでにない「時計文化史」だそうです。
「機械式時計は、人類の歴史を変えた大発明の一つです。なのに、技術的側面と文化的側面が別々に語られてきたせいで、 いまひとつ重要性が理解されていない。そこを一つにまとめて、時計の歴史的意義を明らかにしたいと思っています」。
そんな山田さんは、文化・芸術にお金を使うことに、社会がもっと目を向けてほしいと思っているそうです。
「そもそも、お金は使うためのもの。使いもしないお金を貯め込むのは、使いもしない資格を取るのと同じで、現代の日本人に特有の心理だと思います。 『何かあったとき困らないように』といいますが、何が起きるか予想しないのは一種の思考放棄ですよ。 いくらの家を買えばローンの返済がどうなって、子どもが何人いれば教育費はいくらかかり、病気になれば医療費はこれくらいと、 ちゃんと考えれば人の一生に必要なお金の額は大体、分かるはず。それ以上、貯め込む必要はありません」。
「お金の貯め方や増やし方だけではなく、『上手な使い方』をもっと教えてもいいのではないでしょうか。 そうすれば、他者のためにお金を使う『寄附の文化』も、欧米並みに根付くはず。私自身は、文化や芸術を支援することにお金を使いたいですね。 寄附したくなるほど素晴らしい美術館や劇場は、日本にもたくさんありますから」。
繊細な文化・芸術を語りながら、「お金は使ってなんぼ」という大阪商人の気風ものぞく山田五郎さん。 これからも、「好きになれないはずがない」の精神で得た知識をもとに、独特の切り口で、いろいろな世界を私たちに紹介し続けてくれることでしょう。
![]()
本インタビューは、金融広報中央委員会発行の広報誌「くらし塾 きんゆう塾」Vol.33 2015年夏号から転載しています。